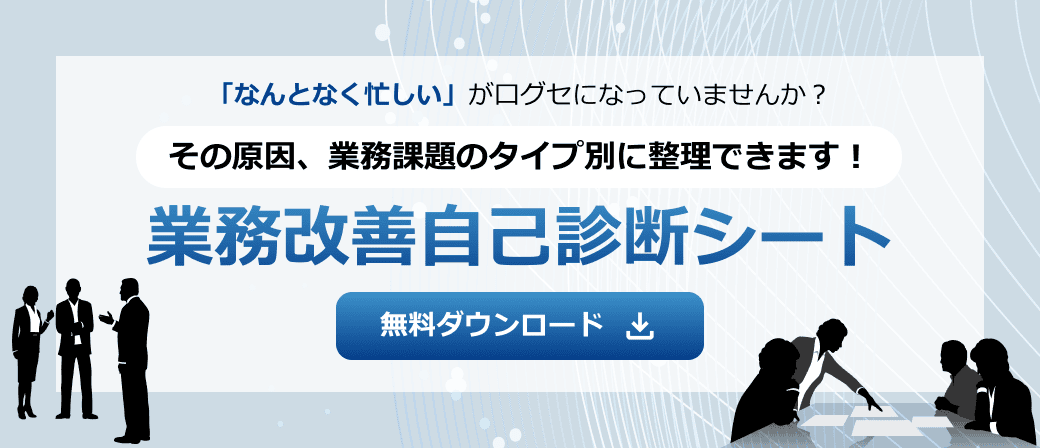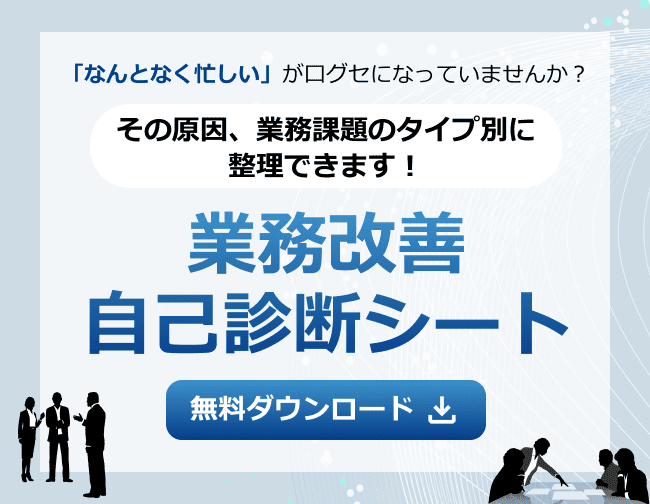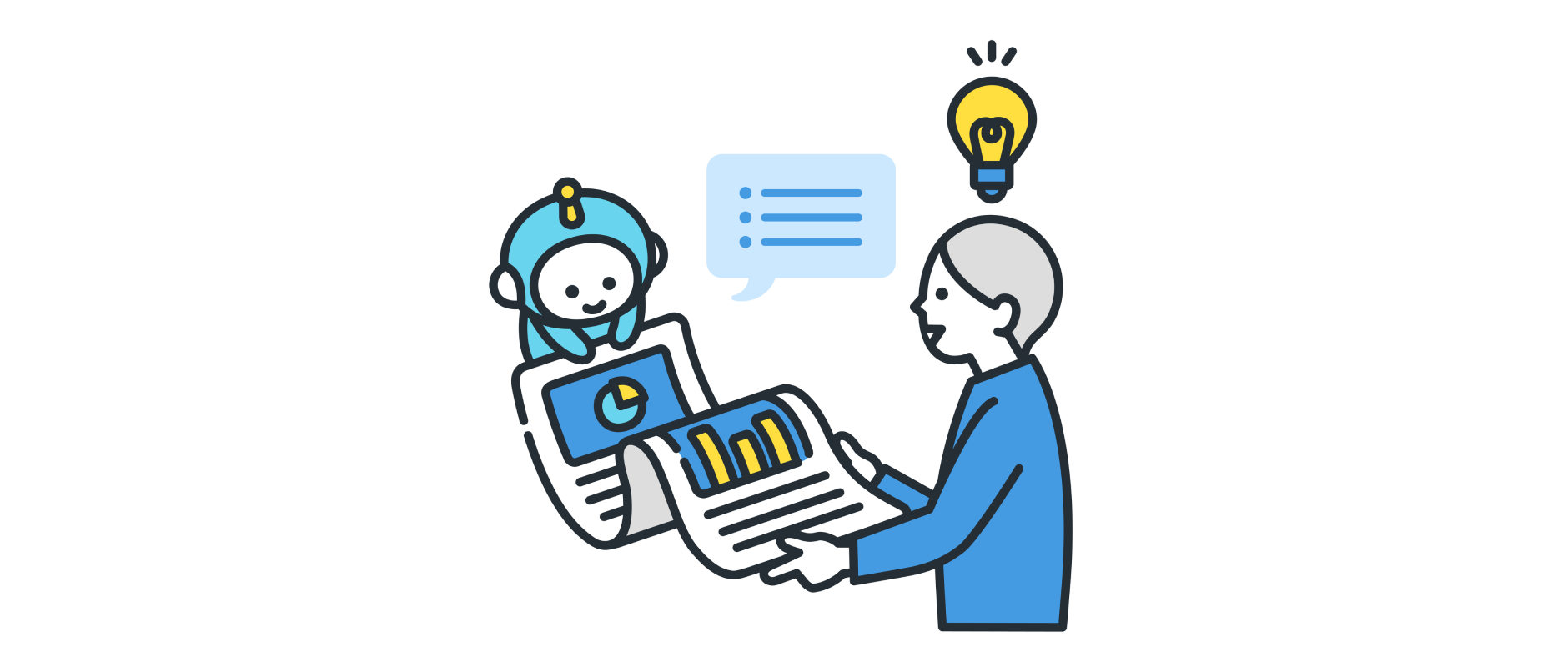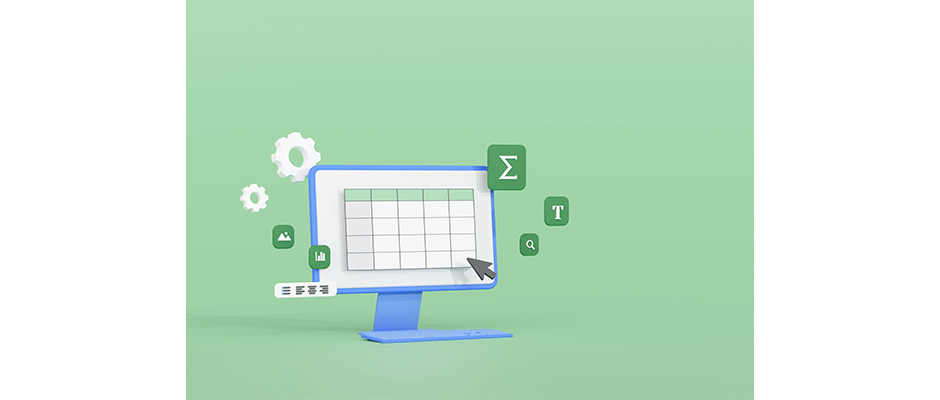【事例3選】業務の見える化とは?生産性向上を実現した企業の取り組みと導入ステップを解説
2025.06.06

業務効率化や生産性向上を実現するために「業務の見える化」は重要な取り組みです。組織の課題解決や業務改善を効果的に進めるために現状把握が必要となりますが、具体的に何をどう進めればよいのか、どのような効果が得られるのかイメージしづらい面があります。
本コラムでは、業務の見える化を行い業務改善に成功した企業の事例や、見える化を行うポイントを紹介します。
業務の見える化とは? 可視化との違い
業務の見える化とは、組織内の仕事の流れやプロセス、情報、課題などを可視化し、関係者全員が共通認識を持てるようにする取り組みです。目に見えない業務の流れや暗黙知を形式化することで、業務の標準化や効率化にも発展させます。
主な目的は、業務の非効率な部分や問題点を明らかにし、改善につなげることにあります。結果として、個人に依存した業務知識やノウハウを組織の資産として共有するといった、いわゆる属人化解消にも大きな効果があります。
また「業務の見える化」と「業務の可視化」は似た言葉ですが、可視化はデータやプロセスを目に見える形にすることを指す一方、見える化はそれに加えて問題点の把握や改善、共有までを含む概念です。例えば、業務プロセスを図式化する段階が可視化であり、それを基に無駄な工程を特定し改善する活動が見える化と言えます。ただし「業務の見える化」=「業務可視化」と同一の用語で使われるケースも多く見られます。
なぜ業務の見える化が必要なのか
業務の見える化が注目されている背景には、業務の標準化といった品質向上の面と人材不足への対応、働き方改革の推進やリモートワークの普及といった社会的要因があります。特に、リモートワークの増加により、業務状況の把握が難しくなる中、業務の見える化による業務の共通認識化により、離れた場所からでも業務状況を共有・把握しやすくなります。また、少子高齢化による人材不足に対応するため、業務効率の向上も急務となっています。
業務の見える化で得られる5つのメリット
業務の見える化を実施することで、企業にはさまざまなメリットがもたらされます。
業務の標準化と品質向上
業務の見える化により、ベストプラクティスを特定した標準化が可能になります。標準化された業務プロセスは品質のばらつきを減少させ、安定したサービス提供を実現します。
人員不足への対応と生産性向上
業務の見える化によって無駄な工程を特定し、業務を効率化することで限られた人員でも高い生産性を維持できます。また、新人の教育時間短縮にもつながり、早期戦力化が可能になります。
問題点の早期発見と迅速な対応
業務の見える化により、従来は気づかなかった問題点を浮き彫りにできます。例えば、業務フローの見える化によって重複作業や手戻りの発生箇所が明確になり、工程間の連携ミスや情報伝達の遅延などの問題点も可視化されます。
ナレッジの共有と属人化の解消
業務の見える化は、個人が持つ暗黙知を形式知に変換し、組織全体で共有することを促進します。これにより特定の人にしか分からなかった業務プロセスやノウハウを組織の財産として共有でき、属人化も解消できます。
リモートワーク環境での業務管理の円滑化
リモートワークが普及する中、業務の見える化はリモート環境での業務管理に大きく貢献します。管理職のマネジメント面でも有効です。
業務の見える化による成功事例
業務の見える化によって業務効率化やコスト削減などの成果が出た事例を紹介します。
会計業務の見える化で部門間連携が強化
三井不動産レジデンシャルサービス株式会社では、会計システムのデータ抽出・加工作業に多大な時間を要しており、業務効率化が課題となっていました。そこで会計データの処理を見える化・システム化することで、大幅な業務改善を実現しました。
具体的には、会計システムから抽出したCSVデータを取り込むと、項目を自動的に並び替え、手作業を介さずに必要な帳票を出力できるシステムを構築。これにより、従来7時間を要していた作業が1時間で完了するようになり、約85%の時間削減に成功しました。空いた時間は分析業務に充てられるようになり、業務の質の向上も実現しています。
また特筆すべきは、このシステム化が部門間連携の強化にもつながった点です。経理課の業務は他部門との連携が不可欠ですが、業務の見える化により他部門とのスケジュール調整にゆとりが生まれ、社内コミュニケーションが円滑になりました。同社は業務の見える化を通じて、現場のITリテラシー向上と意識改革につながった手ごたえも感じています。
三井不動産レジデンシャルサービス株式会社様の事例「現場に一貫して寄り添うEUCアドバイザリーサービス」
システム化されない業務を見える化してサイロ化防止へ
富国生命保険相互会社不動産部では、自社における不動産管理業務のシステム対応を外部委託していたため、操作上の不具合や利用頻度が低い帳票の改善などの問題が先送りされる状況が続いていました。この課題を解決するため、DBJデジタルのEUCアドバイザリーサービスを導入し、現場主導型の業務見える化を実施しました。
導入したEUC(End User Computing)システムにより、現場担当者自身がシステムを開発・運用できるようになり、積み残し案件の解消や業務の効率化が進みました。具体的には、案件ごとの課題解決策の提案、開発立会い、モジュールのサンプル提供、汎用テンプレートの作成など、幅広い支援を受けた結果、サービス導入後1年半で100件以上の積み残し案件が解消されました。
また、前任者が作成した引継ぎ困難なEUCシステムの再構築や、実務に即した担当者のITスキルアップ支援、ドキュメント整備により、業務の属人化を防止。さらに、EUC統制の仕組み整備として、完成したEUCシステムの保管庫を作成し、識別管理や改ざん防止策を実施することで、個人管理・重複管理されていた重要データの一元管理が可能になりました。
この取り組みにより、従来の外部委託と比較して約7割の開発コスト削減効果を実現。さらに、業務担当者によるEUCシステム事例のお披露目会を定期的に開催し、課題解決事例を共有する文化が醸成されたことで、部門全体の改善意識が向上し、組織の活性化につながりました。
富国生命保険相互会社不動産部様の事例「ビジネスを進化させる現場発の業務改善、EUCアドバイザリーサービス」
システム要件の見える化がもたらした大幅コスト削減
名古屋臨海高速鉄道株式会社では、消費税法改正対応や駅務機器更新といった大規模プロジェクトを控え、システム改修の適正コスト判断に苦慮していました。社内にシステム専門要員がいないため、ベンダーから提示される見積りの妥当性を客観的に評価できないという課題を抱えていたのです。
そこでDBJデジタルのIT診断サービスにより、約2千頁に及ぶシステム関連ドキュメントを精査し、現行システムの構成や運用実態の見える化を行いました。また見える化の過程で、消費税法改正や駅務機器更改時に実際に必要となる改修範囲と、不要な改修部分を明確に区分することができました。
こうした業務の見える化により、システム要件を精緻に整理した提案依頼書の作成が可能となり、複数ベンダーによる提案型競争入札の実施が可能となりました。その結果、当初見積もりに含まれていた不要な改修部分が削除され、最終的には改修コストの約4割削減という大きな成果を実現。内部にシステム専門知識がなくても、適切なシステム調達判断ができる体制が構築されました。
名古屋臨海高速鉄道株式会社様の事例「IT活用の最適化によってシステム改修費用4割を削減、IT診断サービス」
業務の見える化を行うステップと成功のポイント
業務の見える化を効果的に進めるためには、計画的なアプローチとポイントを押さえることが必要です。ここでは導入から定着までの具体的なステップと、各段階での成功のポイントを解説します。
STEP1:業務実態の分析と課題の可視化
最初のステップは、「何のために見える化するのか」という明確な目的を設定し、現状の業務実態を丁寧に分析することです。部門全員参加や部門横断のワークショップを開催して業務フローを洗い出し、業務の課題やボトルネックを明確化します。
【成功のポイント】システム導入ありきではなく、現場の業務量や困りごとを定量的に分析することが重要です。業務量の可視化から始めることで、改善すべき優先順位が明確になり、効率的な取り組みが可能になります。
この過程では業務の棚卸や業務課題の特定が必要になります。以下のコラムで詳しい方法を解説しているので合わせてご覧ください。
STEP2:定量指標の目標設定と組織内での共有
課題が明確になったら、次に「何のために見える化するのか」という目的と、具体的な数値目標を設定します。この段階で現場部門責任者の理解とコミットメントを得ることも重要です。
課題が明確になったら、次に具体的な数値目標を設定し、組織全体で共有します。この段階で関係者全員の理解と協力を得ることが重要です。
【成功のポイント】「処理時間を30%短縮する」「エラー率を半減させる」など、具体的で測定可能な目標を設定しましょう。ある保険会社では、営業支援部長自らが「事務処理時間25%削減」という明確な目標を掲げたことで、部門全体の取り組みとして定着し、目標達成につながりました。事業部門の責任者が定期的に進捗を確認する仕組みを作ることで、プロジェクトの推進力が高まります。
STEP3:適切な手法の選定と段階的な実行計画の策定
課題と目的に合わせて、適切な業務分析手法や改善アプローチを選定します。そして、全社一斉ではなく、特定部門からパイロット的に始め、成功事例を作ってから展開することが効果的です。
【成功のポイント】現場の実情に合わせた分析手法や改善アプローチを選定することが重要です。業務フローの可視化、業務負荷の定量分析、関係者間の情報共有方法など、課題に応じた最適な手法を選びましょう。
業務改善の具体的な施策に関しては「業務改善アイデア15選!部門別の改善施策を具体的に紹介」もご覧ください。
STEP4:現場参画型の推進と継続的な改善サイクルの確立
業務の見える化を組織文化として定着させるためには、現場部門の積極的な参画と継続的な改善サイクルの確立が不可欠です。
【成功のポイント】現場部門を巻き込んだワークショップの開催や、改善提案の積極的な採用により、当事者意識を高めましょう。また、定期的な振り返りの機会を設け、見える化されたデータを基に業務改善のPDCAサイクルを回すことが重要です。
業務の見える化は効率化に加えて組織の改善意識も向上させる
本コラムでは、さまざまな業界における業務の見える化の成功事例を紹介しました。業務の見える化は課題の発見、改善活動の促進、そして組織文化の変革につながる重要な取り組みです。成功の鍵は、明確な目的設定、現場の参画、ツールや業務フローを最適化する、そして継続的な改善サイクルの確立にあります。業務の見える化に関するご相談や導入支援については、お気軽にDBJデジタルまでお問い合わせください。
 リクルート
リクルート ダウンロード
ダウンロード