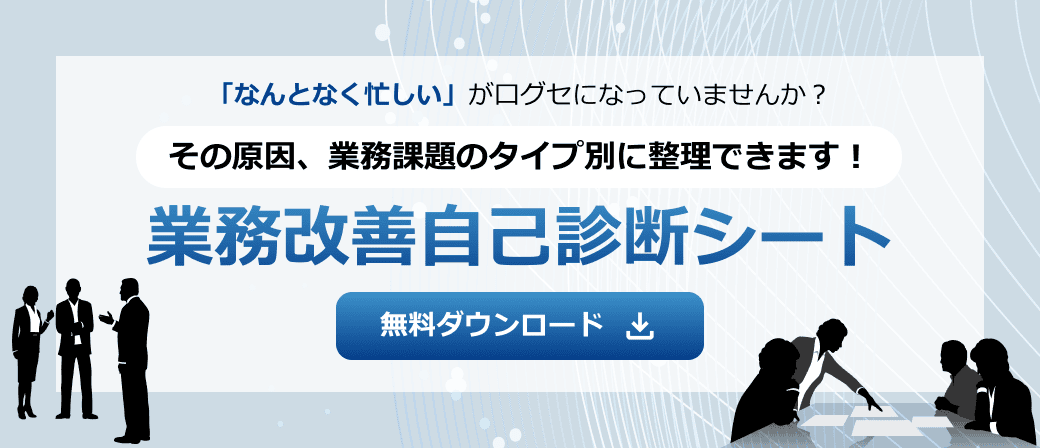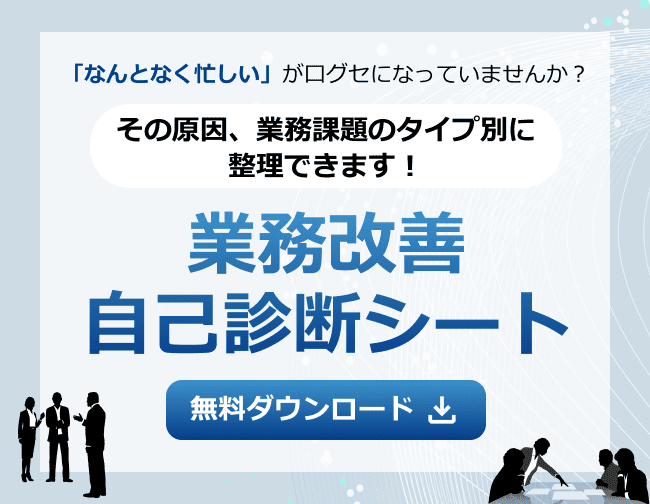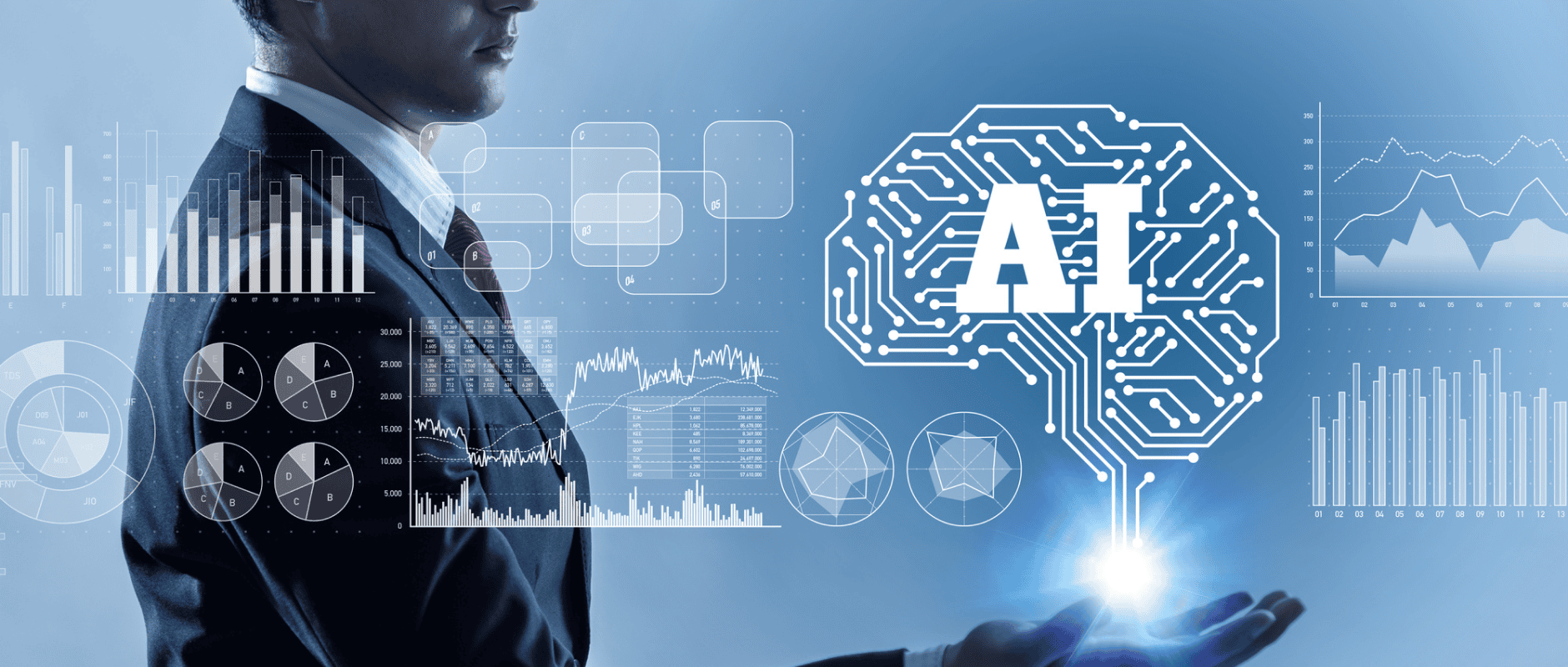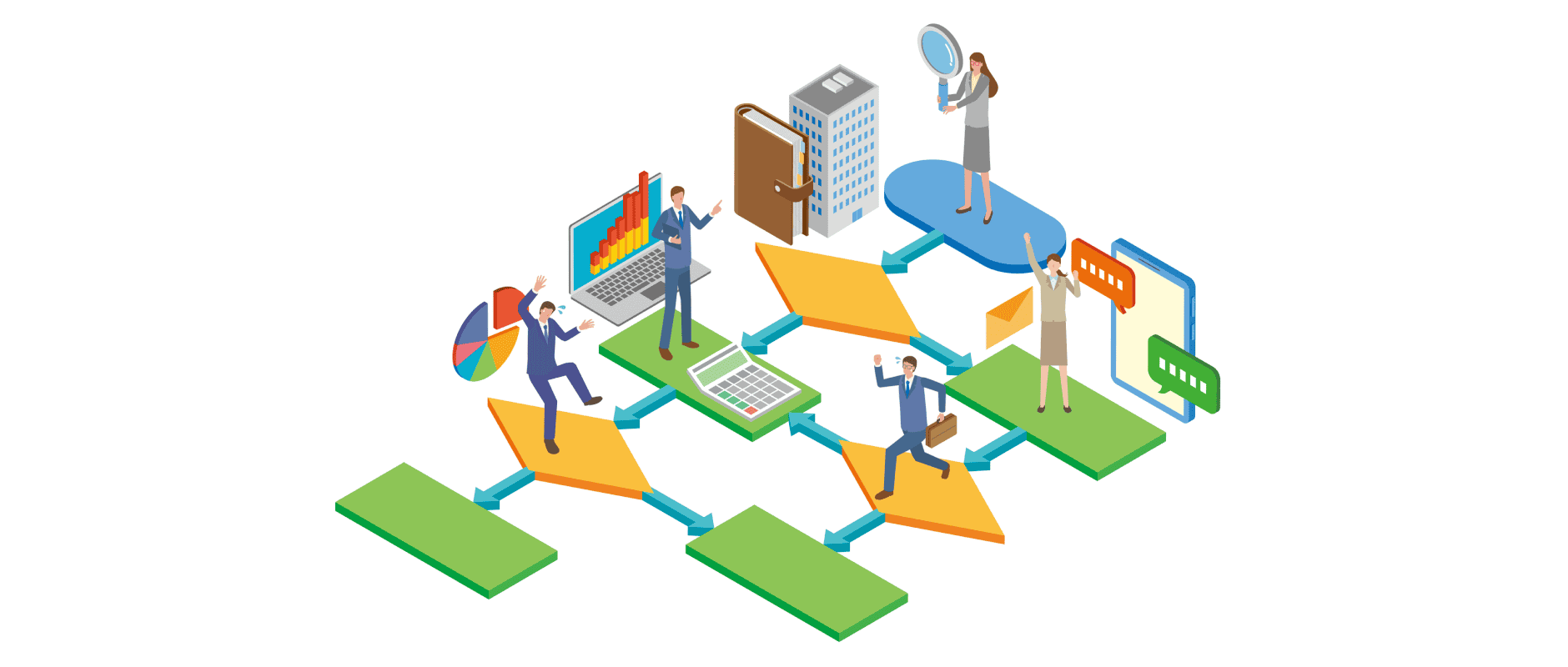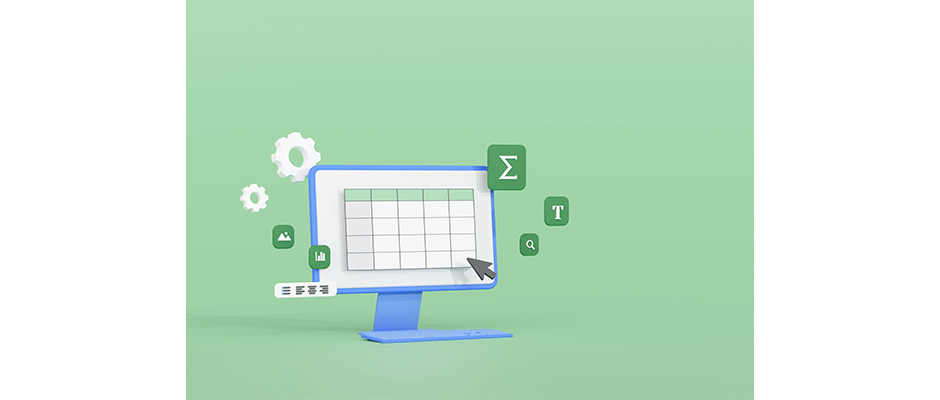残業が多い組織を変える!業務改善による効果的な残業削減の方法とは?
2025.09.29

「残業が減らない」「働き方改革を進めているのに効果が見えない」そんな悩みを抱える組織は少なくありません。HR総研の調査によると、働き方改革への取り組みを行っている企業は多いものの、長時間労働の是正に悩む企業もまた多く残るのが実情です。残業削減の鍵は単なる制度導入や時間制限ではなく、根本的な業務改善にあります。本記事では、残業が多くなりがちな組織の構造的問題を分析し、業務プロセスの見直しから生産性向上まで、実際に効果が出る残業削減のアプローチを詳しく解説します。
残業削減に関して詳しくは「残業が減らない原因とは?残業削減のアイデアや成功事例を紹介」もご覧ください。
残業が多いのはどこから?基準と現状を知る
自社の残業時間が客観的に見て「多い」のか、判断するための基準と残業の平均について説明します。
法的上限と平均残業時間の基準
働き方改革関連法により、残業時間には明確な上限が設けられています。原則として月45時間、年360時間が上限であり、特別条項を結んだ場合でも年720時間、複数月平均80時間以内、月100時間未満(休日労働含む)が絶対的な上限となっています。
実際の平均残業時間は、厚労省の令和7年5月の調査では月10時間程度、転職サービスdodaの調査では月21時間と、調査方法により差があります。一般的に月30時間を超えると「残業が多い」と感じる社員が増える傾向にあります。
業界・職種別の残業時間と「残業が多い」と判断される目安
残業の多さは業界や職種によって大きく異なります。IT業界では月14.7時間、飲食業界では15.1時間が平均的である一方、インフラコンサルタントでは39.4時間と業界によってバラつきがあります。同じ会社内でも部門によって2倍以上の差が生じるケースもあり、業界平均だけでなく部門別の分析が重要です。
過労死ラインとされる月80時間を超える残業は論外として、月30時間を超えると十分な注意が必要です。特に月45時間を超えると法的な特別条項が必要になり、社員のワークライフバランスに深刻な影響を与えます。重要なのは短期的な残業時間削減だけでなく、残業が常態化している原因を分析し解消していくことです。
なぜ残業は減らないのか?組織に潜む構造的問題
残業が慢性化してしまう組織の根本的な問題を3つの観点から分析します。
業務量を正確に見積もれていない
多くの組織で見られるのが、業務量の見積もりの甘さです。「この作業は1日で終わる」という感覚的な判断で業務を配分し、実際には2日かかってしまう等、見積りを超えるケースが頻発しています。
例えば営業部門では、新規顧客開拓の提案書作成を「半日の作業」と見積もっていましたが、実際には市場調査、競合分析、カスタマイズした提案内容の作成で丸2日を要していました。このような見積もりと実態の乖離が解消されずに積み重なることで、慢性的な残業が発生してしまいます。
業務が特定の人に依存してしまう
「○○さんでないとできない仕事」が組織内に蔓延することで、特定の社員に業務が集中し、残業の温床となります。属人化は一見すると専門性の現れのように思えますが、実際には組織全体の効率性を大きく損なう要因です。
例えば経理部門では、月次決算業務が完全に一人の担当者に依存していました。その担当者が休暇を取ると業務が停滞し、復帰後に大量の残業が発生する悪循環に陥っていました。この問題は、業務の標準化とナレッジ共有によって解決できる典型的な事例です。
労働時間を正確に把握できていない
正確な勤怠管理ができていない組織では、残業の実態把握が困難になります。制度やシステム以外にも、部門間や上司と部下のコミュニケーション不足が、業務の進捗状況や負荷の偏りが見えにくくする原因にもなり得ます。
例えばIT企業では、リモートワークの普及により「見えない残業」が増加していました。具体的には在宅勤務中の社員が深夜まで作業していても管理者が把握できず、適切な業務配分の調整ができなといったい状況です。
業務改善で根本的に残業を減らす方法
残業を根本的に削減するため、業務改善を行うための具体的な方法を3つのステップで解説します。
業務可視化で残業発生につながる問題を特定する
残業削減の第一歩は、現状の業務を正確に把握することです。業務の棚卸しを行い、社員一人ひとりがどの業務にどれだけの時間を使っているかを詳細に記録しましょう。残業につながる業務課題を特定して分析することで、改善すべきポイントが明確になります。
さらに、各業務の進捗状況や負荷の偏りをリアルタイムで把握し、必要に応じて業務配分の調整を行う仕組みも重要です。
【具体的な業務可視化の手法】
1. 業務時間記録表の活用
まずは1〜2週間、全社員に業務内容と所要時間を15分単位で記録してもらいます。記録項目は「業務内容」「開始・終了時間」「想定時間vs実際時間」「中断回数」の4つです。
例:営業部Aさんの記録 - 9:00-10:30:提案書作成(想定60分→実際90分、メール対応で2回中断) - 10:30-12:00:顧客訪問準備(想定30分→実際90分、資料が見つからず時間超過)
2. 業務フロー図の作成
各部門で主要業務のフローチャートを作成し、どこで時間がかかっているか、無駄な工程がないかを視覚化します。例えば経理部門では「請求書発行業務」を細分化した結果、承認待ちの時間が全体の40%を占めていることが判明しました。
業務の棚卸や業務課題に関して詳しくは以下もご覧ください。
業務プロセスの見直しと標準化
業務の可視化により問題が特定できたら、次は業務プロセス自体の見直しです。「本当に必要な作業か」「もっと効率的な方法はないか」「自動化できる部分はないか」という観点で業務を分析します。
【業務プロセス改善の4つのアプローチ】
1. 業務の削減(Eliminate)
まず「やめられる業務」を特定します。例えば、ある週次の進捗会議を月次に変更することで、会議と資料作成の時間を削減しました。また、形式的な承認プロセスを見直し、一定金額以下の支出は現場判断にすることで、承認待ち時間を解消するケースもあります。
2. 業務の統合・簡素化(Simplify)
類似した業務をまとめて効率化を図ります。例えば、顧客への定期報告を個別メールから一斉配信システムに変更することで、1件あたり30分かかっていた作業を5分に短縮しました。
3. 業務の自動化(Automate)
定型作業の自動化により大幅な時間短縮が可能です。例えばEUC(End User Computing)を行うならば、Excelマクロにより請求書のデータ集計時間を大幅削減、Excel VBAを使った月次売上レポート作成時間を数日から数時間に短縮といったことが可能となります。
EUCに関して詳しくは「EUCとは?業務効率化を実現する仕組みと導入ステップを解説」もご覧ください。
4. 業務標準化の進め方(standardization)
属人化している業務を標準化するため、ベテラン社員の業務手順をヒアリングし、マニュアルやチェックリストを作成します。新人でも同じ品質で作業できるよう、定期的にマニュアルの見直しも行います。例えば、顧客対応業務では「初回対応は24時間以内に行う」「エスカレーション基準の明確化」「定型回答集の整備」により、誰が対応しても一定の品質を保てるようになりました。
適正な業務配分とスキルマッチング
業務プロセスが最適化されたら、属人化を解消するためにも、人材配置の最適化を行うことが重要です。各社員のスキルレベルと業務の難易度を適切にマッチングさせ、複数の社員が同様の業務を担当できる体制を構築することで、特定の個人への業務集中を防ぎ、組織全体の生産性向上を図ります。
属人化している業務の移管は段階的に進めます。サポート業務から開始し、メイン業務の一部担当、独立業務遂行、完全独立の4段階で進めることで、スムーズに業務が移行できます。さらに、重要業務を複数人で担当できる体制を構築し、主担当が不在でも業務が滞らない仕組みを作ります。
また、スキルマッチングの実践では、まずスキルマトリックスを作成し、社員のスキルレベルを「初級・中級・上級・エキスパート」で評価します。営業部門の例では、新規開拓からプレゼン、契約交渉まで各スキルを可視化し、適切な業務配分を実現しています。
属人化の解消に関して詳しくは「属人化解消の具体的な進め方|リスク分析から効果的な対策まで」もご覧ください。
すぐに実践できる効果的な残業削減の施策やツール
業務改善と合わせて導入すべき具体的な制度やツールについて説明します。
時間管理制度の導入
残業の事前申告制や退社時間の見える化など、時間を意識した働き方を促進する制度の導入が効果的です。ただし、単なる制限ではなく、社員が自律的に時間管理できるような仕組み作りが重要です。
業務効率化ツールの選定と活用
勤怠管理システム、プロジェクト管理ツール、コミュニケーションツールなどを適切に活用することで、業務効率は大幅に向上します。重要なのは、ツールの機能ではなく、組織の課題に合ったツール選定です。
業務の全体像を共有し透明化
可視化された業務フローや進捗状況を全社員で共有し、誰がどの業務を担当しているか、どこにボトルネックがあるかを透明化することが重要です。定期的な業務状況の共有会議や、業務負荷の可視化ダッシュボードの導入により、組織全体で残業削減に取り組む体制を構築できます。
継続的な残業削減には組織風土の変革が必要
残業削減を一時的な取り組みで終わらせず、継続的に改善するならば組織風土の改革が重要です。以下に具体的な例を紹介します。
経営陣のリーダーシップと評価制度の見直し
残業削減を成功させるには、経営陣のリーダーシップと全社員の意識改革が不可欠です。「時間を適切にコントロールし、効率的に成果を出すことが評価される」組織風土を作ることで、持続的な改善が可能になります。人事評価制度においても、労働時間の長さではなく成果や効率性を重視する仕組みへの転換が重要です。
継続的改善の仕組み作り
残業削減の取り組みは一度実施すれば終わりではありません。定期的な業務プロセスの見直し、社員からのフィードバック収集、改善施策の効果測定を継続的に行う仕組みを構築することで、組織の成長とともに働き方も進化し続けます。
業務改善による残業削減で、社員と組織の両方が成長できる環境を
残業削減は単なる労働時間の短縮ではなく、組織の生産性向上と持続的成長を実現する重要な経営戦略です。まずは自社の残業の実態を法的基準や業界平均と比べてどの水準にあるかの客観的把握から始め、組織に潜む構造的問題を正確に特定し、効果的な残業削減につなげていきましょう。
効果的な残業削減には、業務の可視化、プロセス改善、適切なツール導入、そして組織風土の変革まで、様々な組み合わせでの包括的アプローチが必要です。特に重要なのは、経営陣のリーダーシップの下で社員一人ひとりが業務改善に主体的に取り組める環境を整えることです。
業務改善や働き方改革についてさらに詳しく知りたい方は、企業の業務課題の検出から解決アプローチまでワンストップでサポートするDBJデジタルソリューションズにご相談ください。
 リクルート
リクルート ダウンロード
ダウンロード