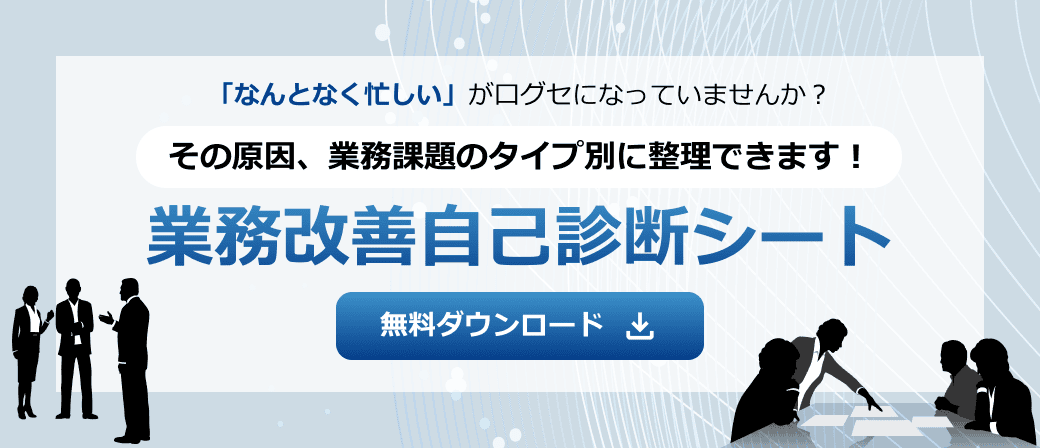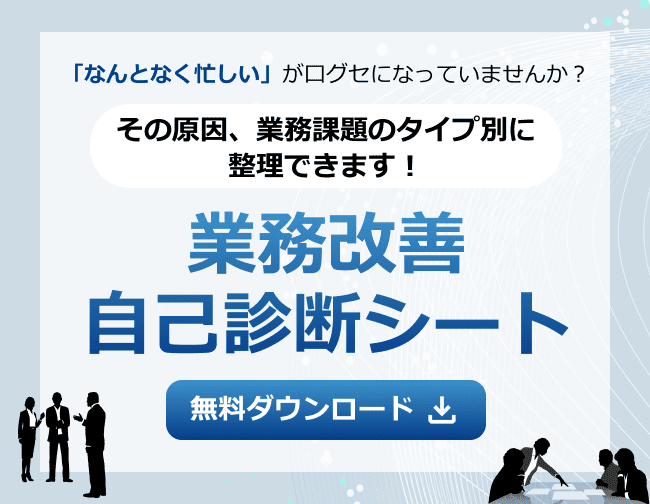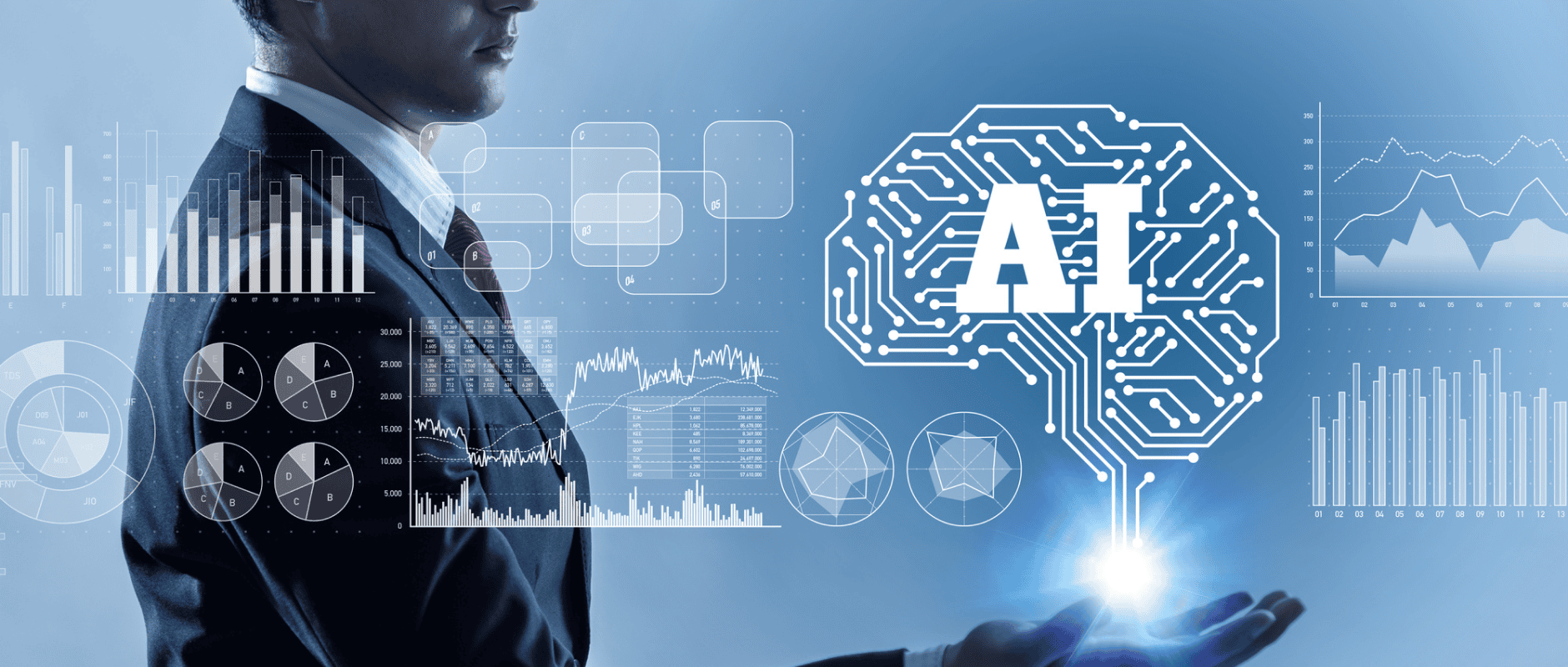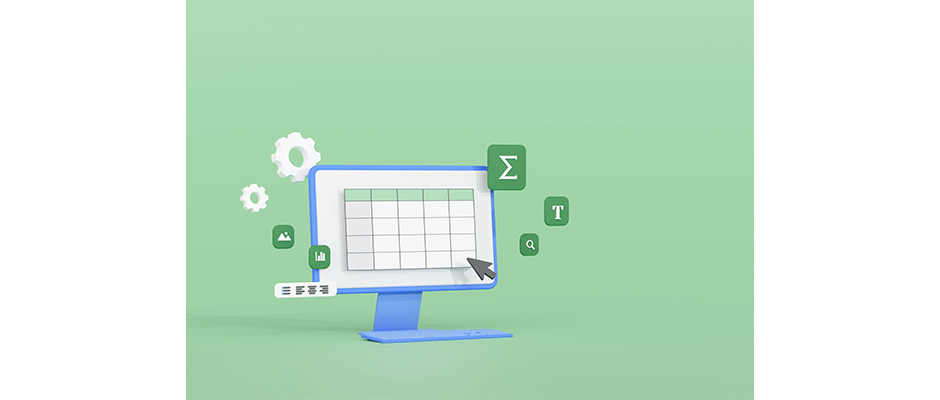わかりやすい業務マニュアルの作り方|効率的な手順と成功のコツを解説
2025.09.29
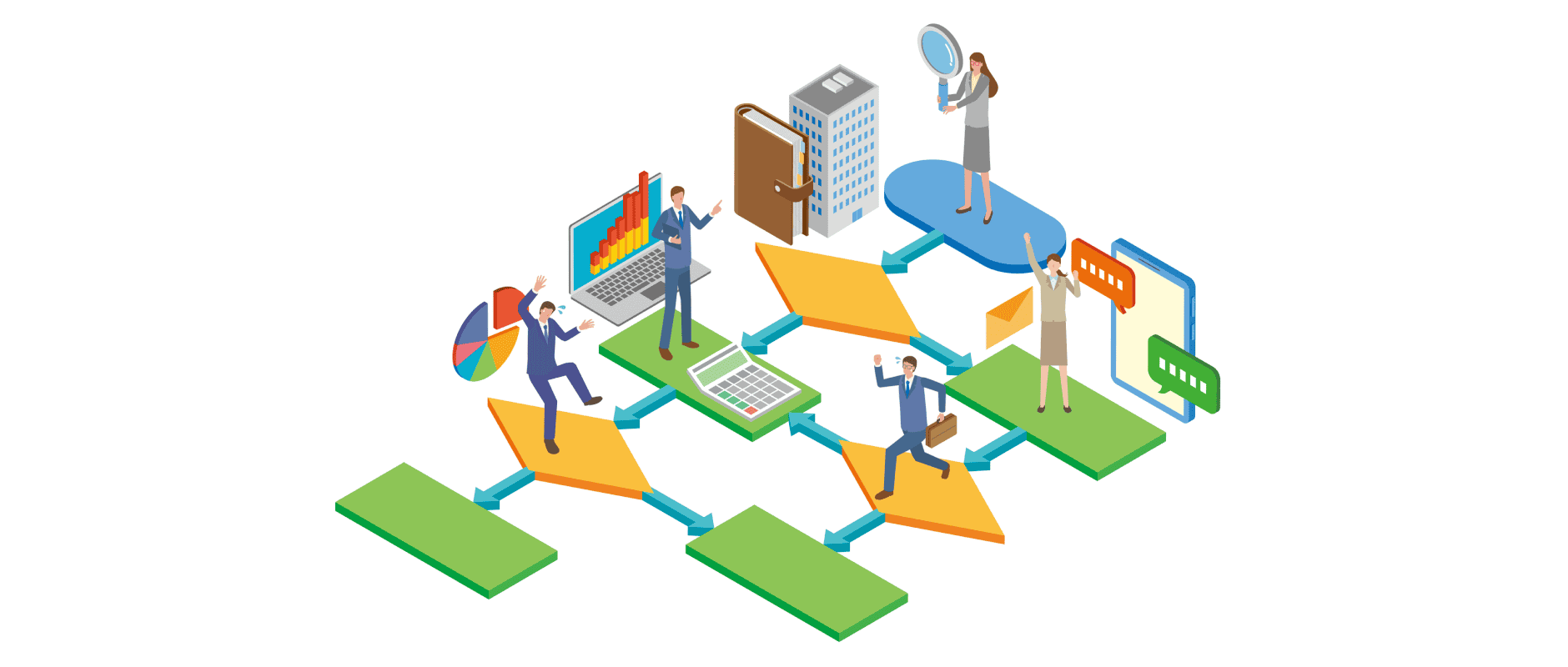
業務マニュアルの作成は、業務の標準化や効率化に大きく貢献します。業務品質の安定、属人化の解消、新入社員の早期戦力化など、その効果は計り知れません。しかし、実際に作成を始めてみると「どこから手をつけていいかわからない」「完成しても誰も読んでくれない」といった壁にぶつかることが少なくありません。
本コラムでは、読み手にとって本当にわかりやすく、実際に現場で活用される業務マニュアルを効率的に作成するための実践的な手順とコツを解説します。
業務マニュアルとは?手順書との違い
業務マニュアルとは、特定の業務を効率的かつ一貫した方法で遂行するために必要な手順、ルール、ノウハウを体系的にまとめた文書です。
業務マニュアルと手順書の違い
- マニュアル:業務の概要と流れ、目的、判断基準を包括的に記載
- 手順書:特定作業の具体的なステップのみを詳細に記載
例えば、営業部門の業務マニュアルには「顧客との関係構築」「提案活動の進め方」などが含まれますが、手順書は「見積書作成の手順」といった個別作業に特化した内容になります。
わかりやすいマニュアルがもたらすメリット
効果的な業務マニュアルは、組織に以下のメリットをもたらします。
- 業務品質の均一化:経験豊富な社員のノウハウを共有し、誰でも一定水準の成果を出せる環境を整備
- 属人化の防止:特定の社員しか知らない業務をなくし、休暇や退職時のリスクを回避
- 教育時間の短縮:新入社員が自主学習できるため、指導者の負担軽減と教育の標準化を実現
特に業務品質の均一化と属人化の防止への貢献は大きいです。これらのメリットを得るためには、マニュアル作成前の準備段階が極めて重要になります。
属人化の解消に関して詳しくは「属人化解消の具体的な進め方|リスク分析から効果的な対策まで」もご覧ください。
マニュアル作成を成功させるポイント
わかりやすい業務マニュアルを作成するためのポイントを解説します。
事前準備がとても重要(目的・対象者・対象業務の設定)
マニュアル作成の成否は事前準備で決まります。「なぜ作るのか」「誰が使うのか」「何の業務をマニュアル化するのか」を明確にし、必要な情報を収集しましょう。
目的設定のポイント:
- 具体的な数値目標を設定(例:問い合わせ件数を月50件から30件に減少)
- 解決したい課題を明確化(例:顧客対応時間の短縮、品質のばらつき解消)
業務課題に関して詳しくは「業務課題とは?可視化の方法から解決手順までを解説」もご覧ください。
対象業務の選定:
業務のマニュアル化には時間や人的リソースがかかるため、優先順位をつけて作成します。以下の基準で対象業務を選定しましょう。
- 属人化リスクの高い業務
- 品質にばらつきが生じやすい業務
- 新入社員がつまずきやすい業務
- 頻繁に発生する業務(月10回以上など)
対象業務が決まったら、現場の実態を正確に把握するために以下のような方法で情報を収集しましょう。
- 実務担当者への聞き取り調査(手順だけでなく、注意点やトラブル事例も収集)
- 既存資料の洗い出し(過去のマニュアル、手順書、チェックリストなど)
- 業務の実地観察(実際の作業風景を見て、暗黙知を発見)
構成設計とわかりやすい書き方を意識する
収集した情報を読み手にとって理解しやすい順序で整理し、目次構成を設計します。業務の流れに沿った論理的な構成にすることで、迷わず使えるマニュアルになります。
効果的な目次構成の原則:
- 業務の時系列に沿った構成
- 各章のタイトルは行動ベースの表現(「○○の方法」「○○の手順」)
- 緊急時対応や頻繁に参照される情報は独立した章として配置
例えば、顧客対応マニュアルであれば「問い合わせ受付」→「内容確認・分類」→「対応実施」→「結果報告」という流れに沿って章立てします。
5W1Hを活用して情報整理
5W1H(Who、What、When、Where、Why、How)のフレームワークを活用することで、必要な情報の漏れを防ぎ、読み手にとって理解しやすい説明を作成できます。
【会議設営の例】
- Who:会議室予約は総務部の田中さんに依頼
- What:プロジェクターとスクリーンを設置
- When:会議開始30分前までに完了
- Where:3階会議室A
- Why:資料の投影と参加者全員の視認性確保のため
- How:機器操作マニュアルに従って接続
レビューと改善を行う
マニュアルの品質を確保するために、校正とレビューのプロセスは欠かせません。実際の利用者となる社員にマニュアルを使って業務を行ってもらい、不明な点や改善すべき箇所をフィードバックしてもらいます。トライアル期間中に収集した改善点を反映させることで、より実用的なマニュアルに仕上げることができます。
マニュアル作成の4ステップ
準備が整ったら、いよいよ実際のマニュアル作成に取りかかります。効率的かつ確実に高品質なマニュアルを完成させるための手順を解説します。
ステップ1:マニュアルの骨組み作成する
収集した情報を整理し、マニュアル全体の構成と章立てを決定します。詳細な内容は後回しにして、まずは「何を、どの順番で、どの程度詳しく説明するか」の設計図を作成しましょう。
骨組み作成のポイント
- 収集した情報を基に章立てを行い、各章の概要を整理
- 詳細な文章は後回しにし、「何について、どの程度の詳しさで説明するか」を決定
また、テンプレートの活用により作業効率を大幅に向上できます。マニュアルのテンプレートは表紙、目次、各章の基本構成などが含まれているものが使いやすいです。
ステップ2:視覚的要素の追加とレイアウト設計
文章だけでは伝わりにくい情報を、図表・画像・色分けなどの視覚的要素で補強します。読み手が直感的に理解できるよう、見やすいレイアウトを設計しましょう。文字ばかりのマニュアルは読まれにくいため、目で見てわかる視覚的要素を取り入れることが有効です。
- スクリーンショットには赤枠や矢印で操作箇所を明示
- 情報の重要度に応じてレイアウトにメリハリをつける
- 手順説明は番号付きリスト、注意事項は囲みコラムで区別
- 図表やフローチャートを用いて複雑な流れを視覚化
- 色分けやアイコンを使って情報を分類
ステップ3:業務フローをわかりやすい文章で書く
視覚的要素で整理した構成に、文章で業務フローの詳細を具体的に作成します。専門用語の説明や具体例を交えながら、誰でも実行できるように明確な手順を書きまましょう。
文章作成の基本原則
- 一文は60文字以内に収める(文章が長いとわかりづらくなるため)
- 専門用語や略語は初出時に必ず説明を追加
- 具体例を積極的に活用
ファイルの命名規則を決める
例:「ファイル名は『YYYY年MM月DD日_報告書_作成者名.xlsx』の形式で保存する(例:2024年03月15日_売上報告書_田中.xlsx)」
ステップ4:レビューと最終調整
完成したマニュアルを実際の利用者に試してもらい、フィードバックをもとに改善を行います。作成者や管理者目線では完璧でも、現場では使いにくい部分が発見されることがあるため、ここで品質向上を行います。
効果的なレビューの進め方
- 実際の業務環境でのテスト実施:マニュアルを見ながら実際に業務を行ってもらう
- 複数の利用者からのフィードバック収集:経験レベルの異なる社員に試してもらう
- 修正後の再確認:改善した箇所が本当に使いやすくなったかを検証
レビュープロセスでは、実際の利用者となる社員にマニュアルを使って業務を行ってもらい、不明な点や改善すべき箇所をフィードバックしてもらいます。
マニュアルの品質を高める5つのコツ
作成したマニュアルをさらに使いやすく、効果的なものにするための実践的なコツを紹介します。
1.視覚的要素を効果的に活用する
文章中心のマニュアルは読まれにくいため、視覚的要素を積極的に取り入れることが重要です。読み手の負担を軽減し、理解度を向上させる工夫を行いましょう。
視覚的要素活用のポイント:
- 画像・図表の効果的配置:文章での説明が困難な箇所には必ずスクリーンショットや図表を配置
- 色分けとアイコンの統一:重要度や種類ごとに色やアイコンを統一し、直感的に理解できるように
- 余白とレイアウトの工夫:情報を詰め込みすぎず、適度な余白で読みやすさを確保
- フローチャートの活用:複雑な判断プロセスは文章ではなくフローチャートで表現
2.簡潔で統一された表現の使用
読み手の混乱を防ぐため、文体や用語を統一しましょう。特に用語に関しては担当者や部署によって呼び方が異なることも多いため、マニュアル内で使用する用語を事前に定義し、一貫して使用することが重要です。
表現統一のポイント:
- 文体の統一(手順説明:「○○を行います」、注意事項:「○○に注意してください」)
- 用語の統一(同じ概念は常に同じ用語を使用)
- マニュアル作成開始時に用語集を作成し、チーム内で共有
3.具体的な数値と例示の活用
抽象的な表現ではなく、具体的な数値や例を示すことで、読み手の理解度と実行精度が大幅に向上します。
具体例の示し方:
- 時間:「しばらく待つ」→「約3分間待つ」
- 分量:「適量」→「A4用紙3枚程度」
- 費用:「交通費:新宿駅から品川駅まで、JR山手線利用、片道160円」
4.注意点・トラブル対応の記載方法
予期せぬ問題やエラーに対して適切な対応方法を明記します。重要度に応じた表現の使い分けと、具体的で実行しやすい説明を記載しましょう。
効果的な注意点の記載:
- 重要度に応じた表現の使い分け(※軽微な注意、重要な注意、禁止事項など)
- トラブル対応は「症状」「原因」「対処法」の3点セットで説明
例:「症状:システムにログインできない、原因:パスワードの期限切れ、対処法:システム管理者に新しいパスワードを申請する」
5.更新・管理しやすい形式の選択
長期的に活用されるように、以下も考慮することで運用効率が向上します。
管理しやすい形式の選択:
- ファイル形式:編集の容易さ(Word、Googleドキュメント)と配布の便利さ(PDF)を考慮
- バージョン管理:ファイル名に作成日やバージョン番号を含める
- 命名規則例:「営業マニュアル_v2.1_20240315.pdf」
マニュアル運用後の注意点
継続利用やマニュアル未更新によるミスを防ぐためにも、作成後も定期的な見直しを行うことが非常に重要です。業務プロセスの変更、システムの更新、法規制の改正などに対応するため、半年から1年に一度はマニュアルの内容を見直し、必要に応じて更新を行いましょう。常に現場で利用されるように、継続的に改善することがマニュアルの陳腐化を防ぎます。
実用的なマニュアルを作成して効率化と属人化解消を行おう
わかりやすい業務マニュアルの作成は、企業の生産性向上と業務品質の標準化において大きく貢献します。
作成の際に重要となるのはまずは基本的な構成でマニュアルを完成させ、実際の運用を通じて段階的に改善していく姿勢です。社員からのフィードバックを積極的に収集し、定期的な見直しを行うことで、マニュアルは組織にとってなくてはならないツールに成長していきます。
業務マニュアルの作成をはじめ業務効率化でお困りの際は、ぜひDBJデジタルにご相談ください。業務改善を総合的にサポートするDBJデジタルでは、貴社の課題に最適なソリューションをご提案いたします。
 リクルート
リクルート ダウンロード
ダウンロード