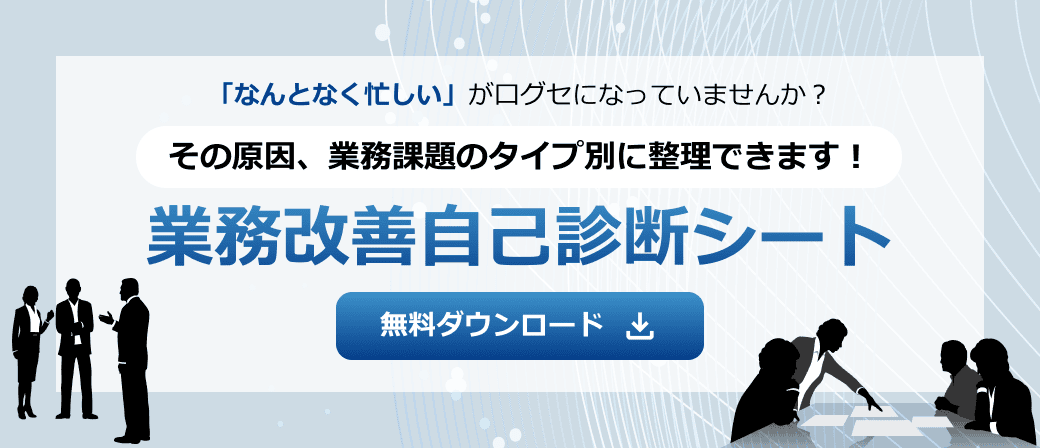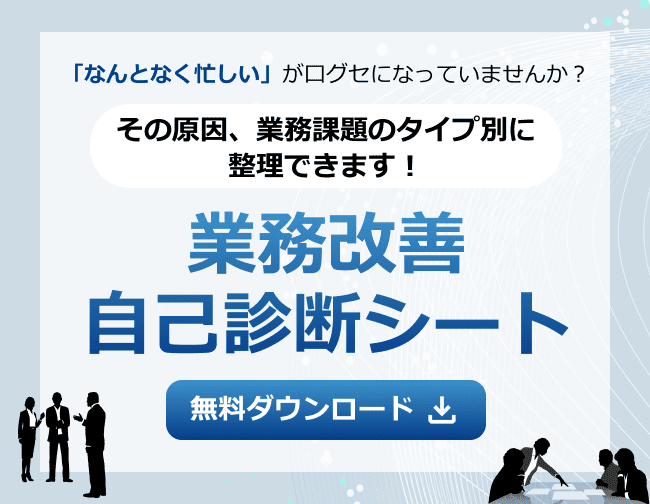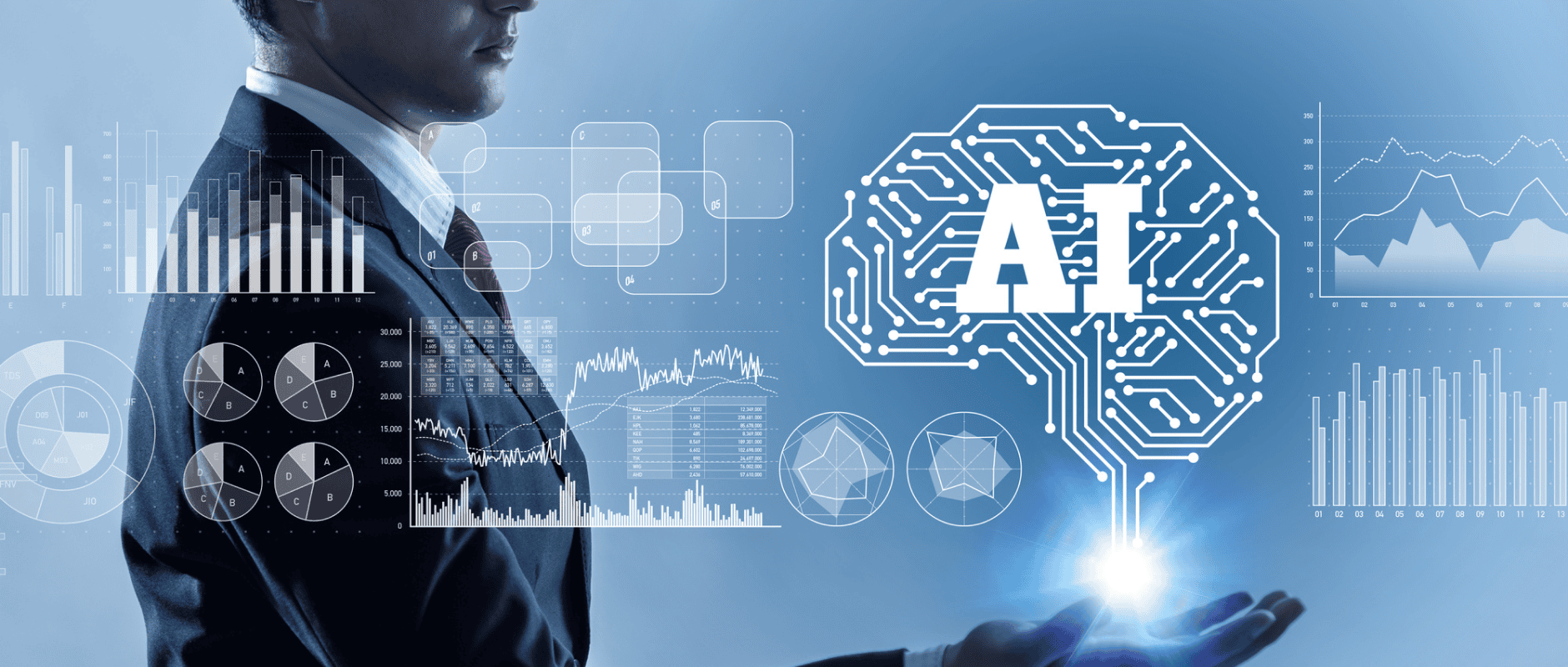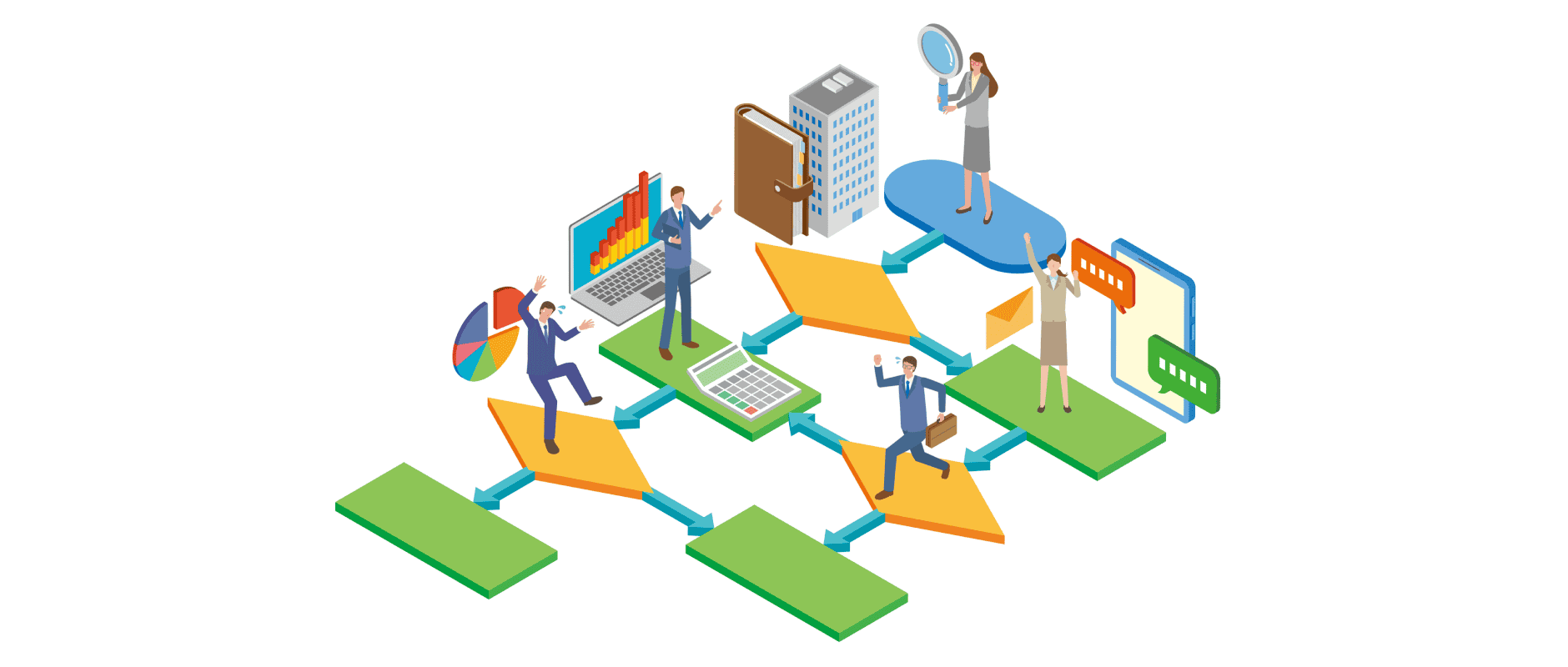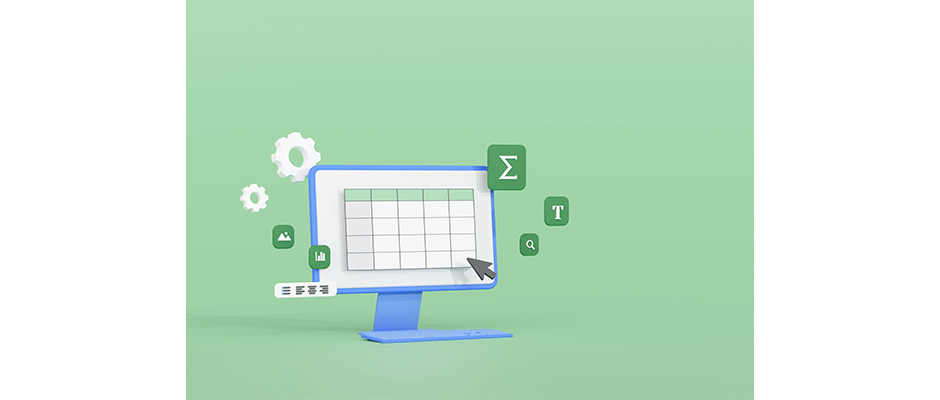自作で業務効率化ツールを作るには?4つの方法と実践ステップを解説
2025.09.29

労働人口の減少や業務の多様化により、業務効率化への取り組みが急務となっています。しかし、根本からの業務改革を図るには時間がかかるうえ、市販の業務効率化ツールを導入するにはランニングコストの問題もあります。こうした課題を解決する手段として、社内での自作ツール開発が注目されています。例えば業務効率ツールを開発したり、EUC(End User Computing)の考え方を取り入れることは有効です。
本コラムでは、技術的な知識が限られた担当者でも取り組める自作ツールの開発手法から、業務効率化を成功に導くためのポイントを解説します。
自作可能な業務効率化ツールの種類と特徴
企業で自作できる業務効率化ツールは、技術レベルや開発環境によって大きく4つのカテゴリーに分類されます。
ノーコード・ローコードプラットフォーム
最も身近で取り組みやすいのが、プログラミング知識を必要とせず、直感的な操作でアプリケーションを構築できるプラットフォームの活用です。Microsoft Power Platform、kintoneなどを活用し、技術的な知見がなくても顧客管理システムや在庫管理システムを短期間で開発することができます。
Excelの自動化ツール
ノーコード・ノーコードと同様に身近で取り組みやすいのが、Excelをベースとした自動化ツールです。VBA(Visual Basic for Applications)を活用することで、データ処理や帳票作成の自動化を実現できます。例えば、複数拠点の売上データを自動統合し、グラフ付きレポートを数分で完成させることが可能です。既存のExcel運用との親和性の高さから導入しやすく、EUC(End User Computing)の考え方に最も適したアプローチとも言えます。
EUCに関して詳しくは「EUCとは?業務効率化を実現する仕組みと導入ステップを解説」もご覧ください。
クラウドサービス連携型ツール
既存のクラウドサービスのAPIを活用し、複数のサービスを連携させることで業務フローを自動化するツールです。複数のシステムにまたがる業務やデータを短時間で連携し、データの転記や作業の重複等の解消が可能です。
プログラミング言語で構築する本格システム
Python、JavaScriptなどのプログラミング言語を使用した本格的なシステム開発です。複雑な業務ロジックにも対応できる反面、技術的な専門知識と開発期間が必要になります。
ツールを自作する3つのメリット
自作ツールの開発を検討する際は、メリットとデメリットを把握し、自社の状況と照らし合わせて判断することが重要です。まずは主なメリットを3つ説明します。
導入・運用コストを大幅に削減できる
市販の業務効率化ツールや買い切り型のパッケージソフトは導入・運用費用に一定以上のコストが発生します。規模によっては、多額のコストが発生することも珍しくありません。自作ツールの場合は開発時の人件費と最小限のインフラ費用のみで済むため、長期的に大幅なコスト削減ができます。
開発の自由度を高められる
市販ツールは汎用性が高いため、独自の業務フローや特殊要件への対応が難しいですが、自作ツールであれば柔軟に対応できます。既存の業務フローを変更することなく、現在の運用に最適化されたツールを開発できるため、ツール導入時の説明・学習コスト、現場の混乱や抵抗を最小限に抑えることができます。
業務の変化にスピーディーに対応できる
通常のシステムでは、ベンダーを介するため、カスタマイズや更新作業などに時間がかかりますが、自作であれば変更が必要なタイミングですぐに社内にて修正できるため、迅速な対応が可能です。
ツール自作で発生する3つのデメリット
ツールを自作することで発生する3つのデメリットを説明します。
開発・保守に人的リソースが必要
自作ツールの開発には、設計から実装、テスト、運用までの各フェーズで人的リソースが必要になります。特に中堅企業以上では、複数部門での利用を想定した設計や、セキュリティ要件への対応が求められるため、専門的な知識を持つ担当者の確保や外部委託の検討が重要になります。
技術的ハードルを乗り越える必要がある
プログラミングスキルやシステム設計の知識が必要です。データベース設計やセキュリティ対策などの専門的な技術が求められる場面では、十分な知識を持つ担当者の確保が課題となります。特に大企業では、情報システム部門との連携やガバナンス体制の構築も重要な要素となります。
※自作ツール開発でお困りの企業様には、DBJデジタルのEUCコンサルティングが最適なツール選定から運用、自走支援まで包括的にサポートいたします。
セキュリティリスクと属人化の課題を抱える
セキュリティ対策やバックアップ体制の構築を自社で行う必要があります。また、開発担当者が退職した場合のシステム保守が困難になる属人化のリスクも存在します。中堅企業以上では、コンプライアンス要件やデータガバナンスの観点からも、適切な管理体制の構築が不可欠です。
属人化の解消に関して詳しくは「属人化解消の具体的な進め方|リスク分析から効果的な対策まで」もご覧ください。
自作ツールで業務効率化できる業務領域
自作ツールで特に効率化できる業務領域を紹介します。
データ処理・集計業務の自動化
複数のシステムやファイルからデータを収集し、統合・加工する業務は自作ツールの得意分野です。例えば、複数のECモールから売上データを収集し統一フォーマットで集計する作業を、3時間から5分程度に短縮できます。中堅企業以上では、基幹システムとの連携や大量データの処理が求められることも多く、EUCの考え方を活用した段階的なアプローチが効果的です。
EUCの活用に関して詳しくは「EUCの活用で効率化できる業務とは?経理・営業・人事部門ごとの活用テクニックを解説」もご覧ください。
定型的な報告書・資料作成業務
毎月作成する売上レポートや定期的な進捗報告資料など、フォーマットが決まっている資料作成業務は自動化の効果が高い領域です。
顧客管理・営業支援業務
顧客情報の管理や営業活動の記録、フォローアップの管理など、営業部門の業務効率化も自作ツールで対応可能です。
在庫管理・発注業務の効率化
在庫レベルの監視と自動発注システムの構築は大きな効果をもたらします。在庫を下回った商品を自動検出し、最適な発注量を算出して発注書を自動作成するシステムを構築できます。
業務効率化ツール自作の具体的ステップ
自作ツールを開発するためのステップを解説します。
STEP1:業務課題の洗い出しと対応すべき課題の特定
現在の業務フローを詳細に分析し、効率化が可能な作業を特定します。作業時間の測定、手作業による処理の頻度、担当者へのヒアリングを通じて、定量的なデータに基づいた課題整理を行います。特に、同じ作業を繰り返し実行している業務や、複数のファイルやシステム間でのデータ転記作業などは、自動化による効果が高い領域として優先的に検討すべきです。
業務課題や業務の棚卸しに関して詳しくは以下もご覧ください。
「効果的な業務の棚卸しとは?|5つの手法と実践ステップを解説」
STEP2:適切な開発手法・ツールの選定
課題の特性と社内の技術レベルを考慮し、最適な開発手法を選択します。シンプルなデータ処理であればExcel VBA、複雑なワークフローの自動化であればPython、ユーザーインターフェースを重視する場合はノーコードツールといった判断基準を設けます。
多くの企業では既存のExcelや、基幹システムから出力されるデータとExcelを組み合わせることで効果的に業務効率化できます。例えば、販売管理システムから出力した売上データとExcelで管理している顧客情報を掛け合わせることで、より詳細な分析レポートを自動作成できます。このようなEUCアプローチにより、大規模な新システム導入を行わずとも、既存資産を活用した効率的なツール開発が可能になります。
ただし、課題解決に必要な技術レベルが高く、時間を要する場合は外部への委託も検討しましょう。
STEP3:要件定義とプロトタイプ作成
開発すべきシステムの詳細な仕様を決定し、実際の業務環境で小規模なテスト運用を実施します。ツールの有効性と問題点を検証し、完璧を求めず、コアとなる機能のみを実装して、実際の使用感と効果を確認することが重要です。
STEP4:本格導入と運用体制の構築
テスト結果を基にツールを改良し、全社展開を行います。同時に、操作マニュアルの作成、担当者への研修、保守・サポート体制の整備を実施し、運用環境も構築しましょう。
自作ツールの導入や運用でお困りの場合は、外部の業務改善コンサル会社を活用することも効果的です。自走支援も含めた包括的なサポートを受けることで、より確実な成功を期待できます。
最初から完璧を目指さず、スモールスタートで始めて業務効率化を実現しよう
業務効率化ツールの自作は、適切なアプローチにより市販ツールでは実現できない自社最適化された効率化を可能にします。重要なのは、完璧を目指さず小さく始めて段階的に発展させる姿勢です。市販ツールを導入した後、自作ツールの追加開発で業務改善のラストワンマイルを埋めていく手法も考えられます。また、EUCの考え方を活用することで、各部門の社員が主体的に業務改善に取り組める環境を整備し、組織全体の生産性向上を実現できます。
DBJデジタルでは、EUCコンサルティングサービスを通じて、お客様の業務特性に応じた最適なツール開発戦略をご提案し、開発から運用まで一貫したサポートを提供しています。業務効率化ツールの自作をご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。
 リクルート
リクルート ダウンロード
ダウンロード