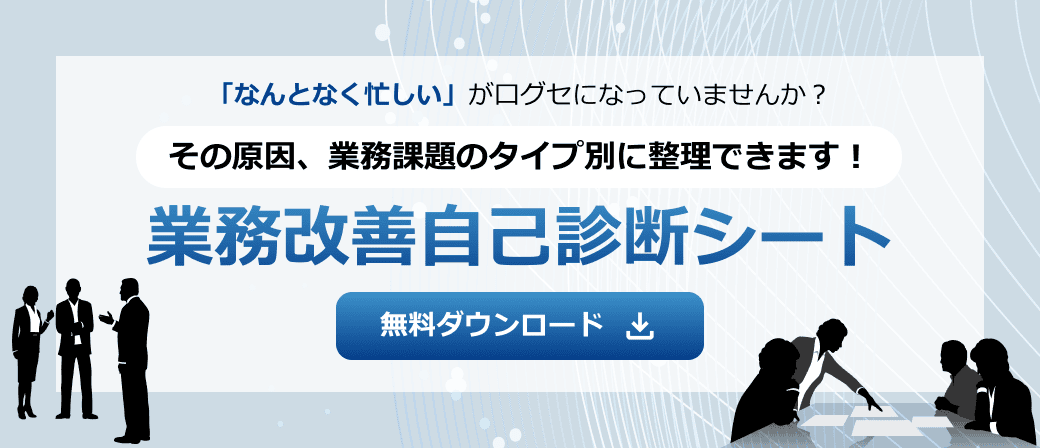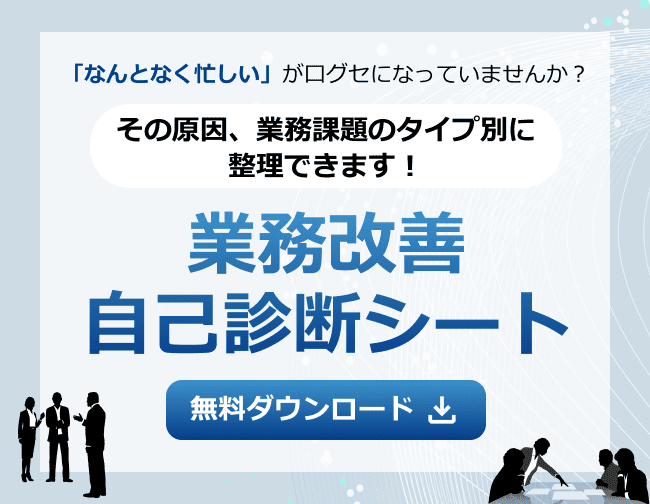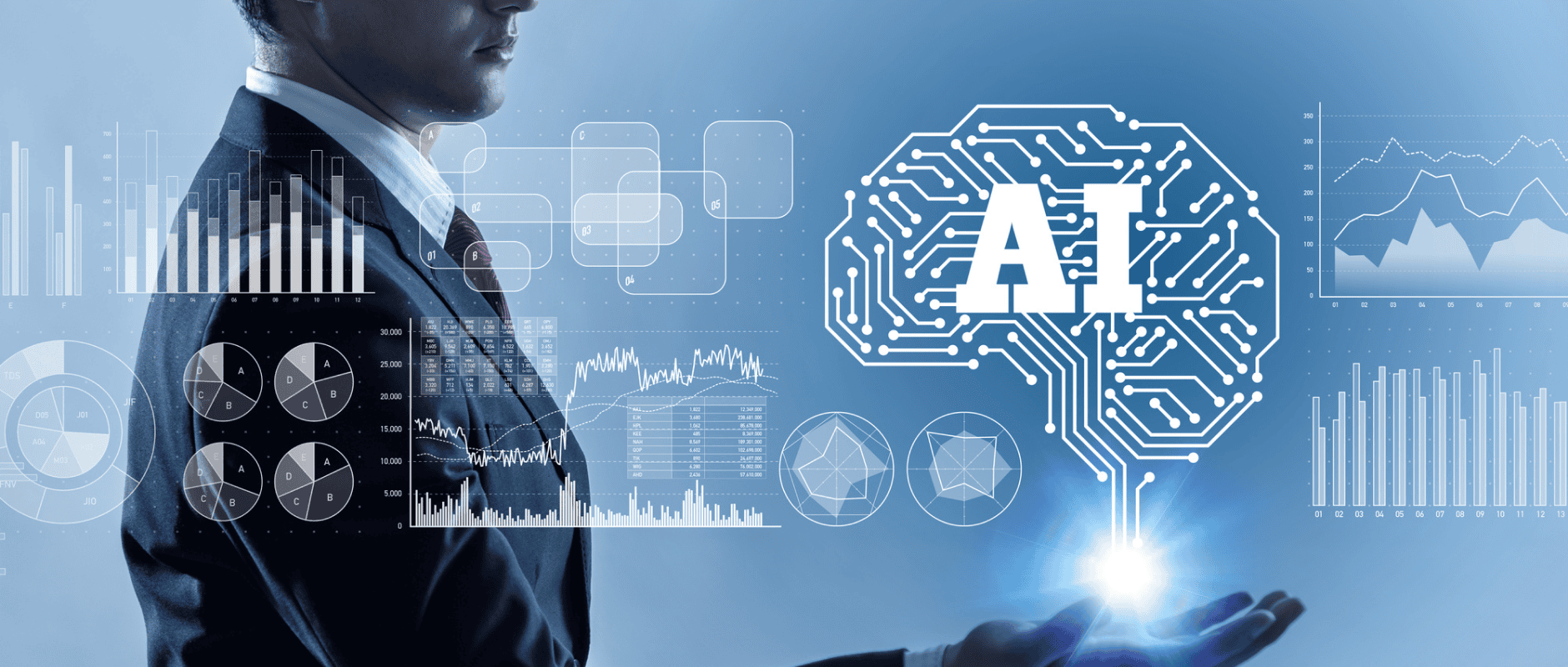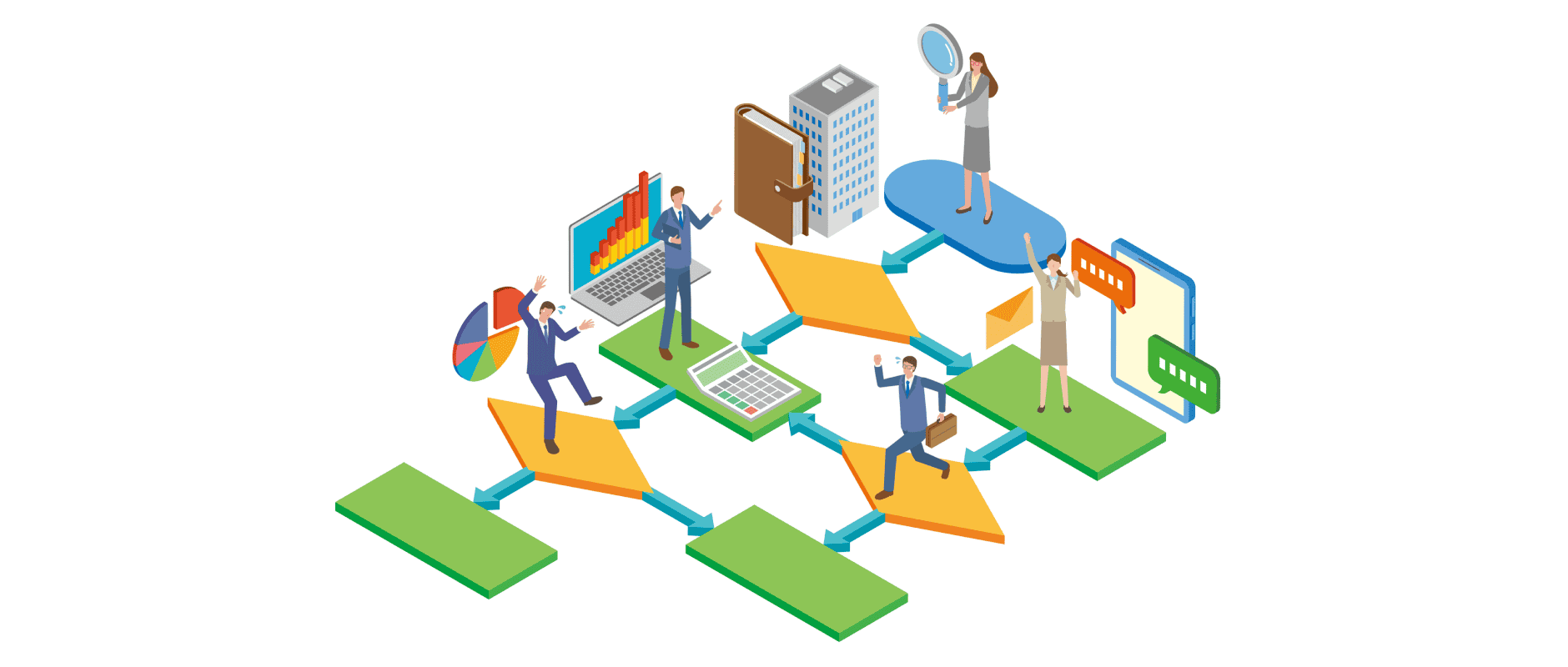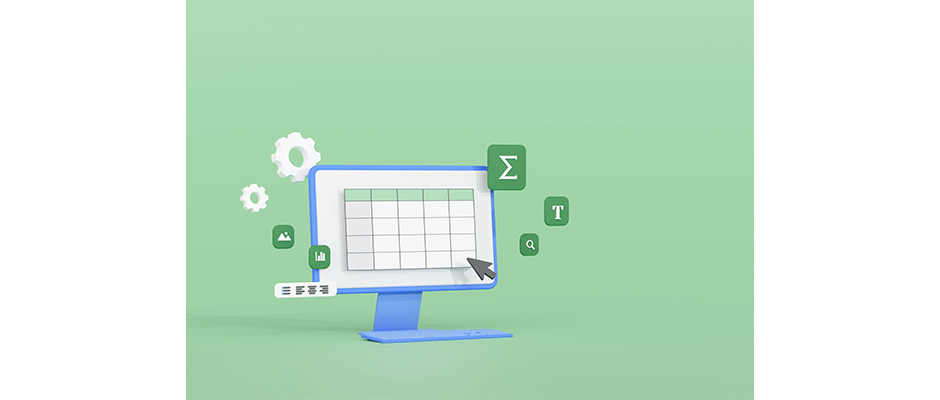残業が減らない原因とは?残業削減のアイデアや成功事例を紹介
2025.07.29
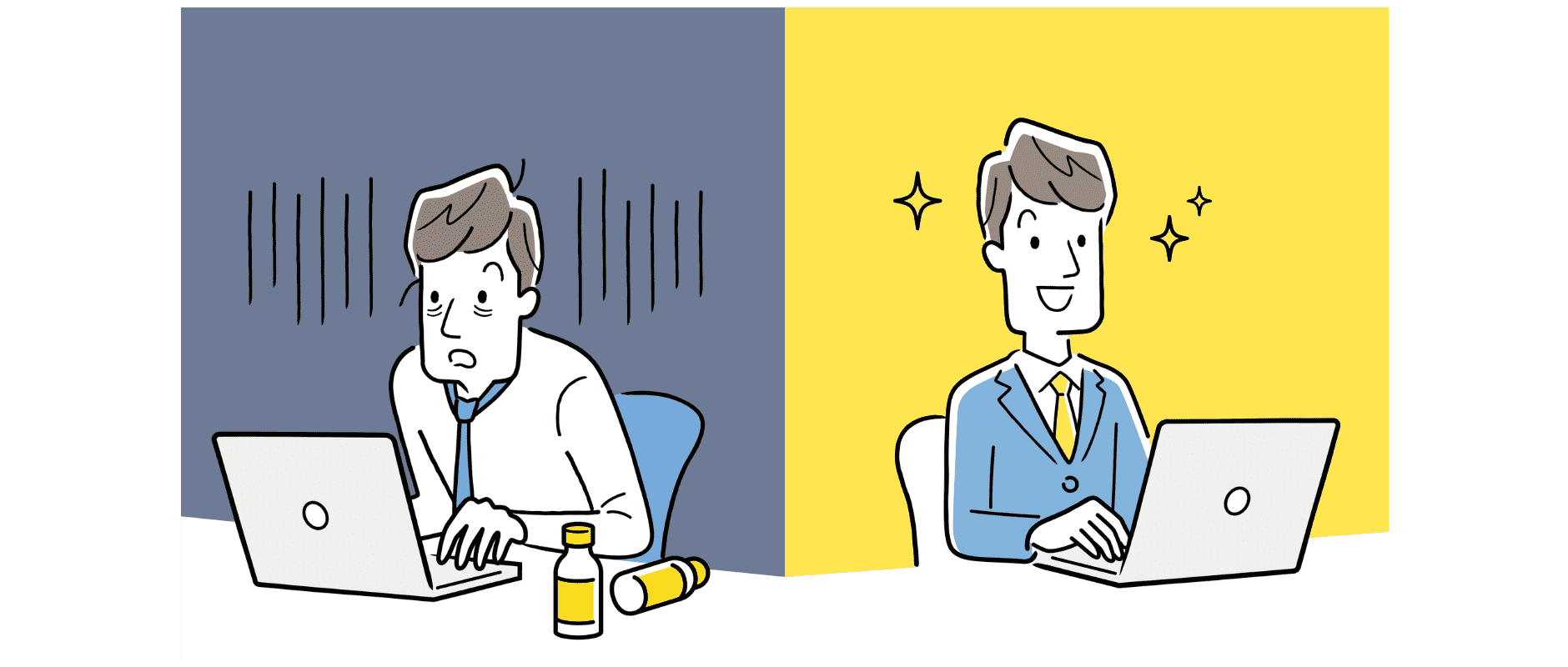
近年、多くの企業が残業の削減に取り組んでいます。法的規制の強化、激化する人材獲得競争、社員のワークライフバランス重視の傾向など、様々な要因から残業削減への取り組みは避けて通れません。しかし、「残業を減らしたい」という意識はあっても、どのような対策が効果的なのか頭を悩ませる企業も少なくありません。本コラムでは、残業が減らない本質的な原因と、効果的な削減方法を解説します。
残業削減が求められる背景
残業削減が企業の重要課題として注目される理由には、法的な要請だけでなく、企業の持続的成長のための必然性があります。
働き方改革の推進
2019年4月に施行された働き方改革関連法により、原則月45時間・年360時間の残業時間上限規制が導入されました。法令遵守の観点からも、残業削減は企業にとって避けて通れない課題となっています。ただし、働き方改革の推進は法令遵守にとどまらず、業務の無駄が見直され、結果的に企業全体の生産性向上が期待できます。
働き方改革関連法について詳しくは厚生労働省の「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」をご覧ください。
働き方改革による生産性向上に関しては「生産性向上で働き方改革が推進する|具体的なアプローチ方法や成功事例を解説」もご覧ください。
採用人材確保の競争激化
少子高齢化による労働人口の減少に伴い、優秀な人材の獲得競争が激化しています。就職活動中の学生や転職希望者にとって、ワークライフバランスは企業選びの重要な判断基準の一つとなっており、長時間労働が常態化している企業は優秀な人材の確保が困難になるリスクがあります。
さらに、将来的な労働人口の減少を踏まえると、そもそも残業しないと業務が成り立たない状況では労働人口が減少の一途を辿る将来に対応できません。今のうちから業務プロセスの抜本的な見直しと改善に取り組み、残業をしなくても効率的に業務が回せる体制を構築することが必要です。
残業が減らない5つの原因
企業が率先して残業削減に取り組んでいるにもかかわらず、なかなか成果が出ない主な原因を紹介します。
業務量が多い
最も基本的な残業の原因は、単純に業務量が多すぎることです。人員削減や業容拡大に伴い、一人当たりの業務負担が増加しているケースが少なくありません。
業務の属人化による特定社員への負担集中
特定の社員しか知らない業務やノウハウが多く、一部の社員に業務が集中する「属人化」も残業の原因となります。業務の可視化と標準化により、特定の社員への負担集中を防ぐことが重要です。
会議や割込み業務で業務がはかどらない
一日の業務時間の多くが会議や突発的な対応に時間が費やされ、本来の業務への注力や対応する時間が取れないことも残業の大きな原因です。
収入確保のため残業代へ依存
残業代を含めて生活給となっている場合、社員自身が「無理にでも残業しないと生活が成り立たない」という考えに陥るケースがあります。
「帰りづらい」職場の雰囲気
日本企業特有の「上司より先に帰りづらい」「部内の社員が残っていると帰りづらい」という職場文化も、残業を助長する一因です。
会社・部署で取り組む残業削減の対策6選
残業が減らない本質的な課題を克服し、継続的に残業を削減するための対策を紹介します。
勤怠管理の可視化
まず取り組むべきは、残業の実態を正確に把握することです。勤怠管理システムを導入し、部署別・個人別の残業時間や残業時の対応業務を可視化することで、問題の所在が明確になります。残業の「見える化」は、対策の第一歩です。
業務マニュアルの整備
残業の原因として、属人化した業務の担当者に負担が偏っている、業務フローが複雑で時間がかかるなどが挙げられます。この解決にはマニュアル作成が有効です。マニュアル作成のためには、まず現状の業務を可視化し、棚卸しすることが重要です。各業務の所要時間、担当者、頻度を明確にし、どこに非効率が生じているかを特定します。その上で属人化を防ぎ、業務を効率化するため、業務マニュアルを整備します。誰でも同じ品質・スピードで業務を行えるよう手順やノウハウを文書化することで、業務の標準化と残業削減を同時に実現できます。
業務の棚卸しや業務の見える化の事例に関しては以下もご覧ください。
「【事例3選】業務の見える化とは?生産性向上を実現した企業の取り組みと導入ステップを解説」
DXツール(EUC・RPA)の導入
業務効率化のためのDX(デジタルトランスフォーメーション)の活用も、残業削減に大きく貢献します。特にEUC(End User Computing)による、業務部門のユーザーが直接システムを利用して、必要なアプリケーションやデータベースを作成・運用する仕組みはコストパフォーマンスの非常に高い取り組みです。この他にも、RPAによる定型業務の自動化、クラウドサービスによる情報共有の効率化など、テクノロジーを活用した業務改革は残業削減に大いに効果があります。
EUCと活用に関して詳しくは以下もご覧ください。
「EUCとは?業務効率化を実現する仕組みと導入ステップを解説」
「EUCの活用で効率化できる業務とは?経理・営業・人事部門ごとの活用テクニックを解説」
労務管理制度の改善
労務管理制度の見直しにより、働き方の柔軟性を高められます。例えばフレックスタイム制度の導入により、社員が自分の生活スタイルに合わせて勤務時間を選択できるようになります。また、週に1〜2日全社で定時退社を徹底する「ノー残業デー」の導入なども効果的です。ただし、これらは形式的な導入に終わらないよう、経営層が主導して継続的に取り組むことが不可欠です。
テレワークの導入
通勤時間の削減や集中できる環境が確保できることからも、テレワークは業務効率向上にも大きく貢献します。業務効率の向上だけでなく、育児や介護と仕事の両立を支援し、多様な人材の活躍を促進する効果もあります。
評価制度の見直し
残業の多さを評価する風潮が社内に顕在する場合、評価制度の見直し検討が必要です。「残業時間ではなく成果で評価する」という方針を明確にし、短時間で成果を上げた社員を評価・表彰する仕組みを導入することも必要です。
すぐに取り組める残業削減のアイデア4選
会社全体での対応は長期的な対応となりがちですが、部署や個人単位の取り組みですぐに実践できる残業削減のアイデアを紹介します。
残業の事前申請
残業をする際は事前に上長承認を必要とする制度も効果的です。残業を「特別なこと」と意識づける効果があります。10時間、20時間を超過する場合など、職種や等級に応じて申請条件を変えるのも有効です。
業務優先順位の明確化
日々の業務に優先順位をつけ、重要な業務に集中することで、残業を減らせる場合があります。必要な時に必要な業務に取り組む文化の醸成・定着が重要です。
集中タイムの設定
打ち合わせや電話対応を制限し、集中して業務に取り組める時間帯を設定する「集中タイム」も効果的です。部署単位で個人・業務別に時間を決める、社員の裁量に任せてスケジューラー登録して配慮しあうなど、業務の性質に合わせて、集中できる環境を整えます。
ノー残業デーの導入
週に1〜2日、部署単位で定時退社を推奨する「ノー残業デー」は、制度導入が不要で即座に実践できる効果的な対策です。全社的な制度化が難しい場合でも、部署やチーム単位から始められるため、導入のハードルが低く、残業削減の意識づけにも効果があります。
上記以外にも、業務改善のアイデアや具体例は以下もご覧ください。
残業削減の成功事例
残業削減の成功事例を紹介します。
週休3日制導入と月平均残業時間を3分の1へ大幅削減
株式会社サタケでは2010年から段階的に残業削減に取り組みました。当初は水曜日と給与支給日のみだったノー残業デーを、金曜日、月曜日と拡大し、2014年度からは原則毎日定時退社のオールノー残業デーへと移行。並行して業務の見直しも進め、副社長による約400人の社員へのヒアリングにより、約3〜4割の無駄な業務が存在することが判明しました。業務効率化の意識向上と段階的な業務改善により、2009年に月平均23.5時間だった時間外労働時間が、2019年には月平均6.8時間まで減少。さらに2017年度からは夏季限定で週休3日制を導入し、より働きやすい環境を実現しています。時間外労働の削減による給与減少に対しては、業績連動型の特別ボーナスを支給するなど社員への還元も行い、ワークライフバランスの向上と業務効率化を両立させることに成功しています。
出典:厚労省働き方改革特設サイト 中小企業の取り組み事例, 参照日2025年5月28日
残業事前申告制と集中タイムで「残業は特別なもの」意識を浸透
東光コンピュータ・サービス株式会社では、「社員は一番の財産」との考えから健康経営を主軸とした働き方改革に取り組んでいます。2017年から経営トップの「健康宣言」のもと、年間休日120日以上の完全週休2日制を導入し、残業時間削減のため徹底的な効率化を実施。月1回の全体会議を年3回に減らし、残業を事前申告制として「残業は特別なもの」という意識を浸透させました。水曜日のノー残業デーの設定や、「集中タイム実施中!」ののぼりをデスクに置いて話しかけられない環境を作るなど、時間内での業務完了を促進。ITリテラシーの高い企業の強みを活かし、サブスクリプションサービスの100%活用やサテライトオフィスの設置により通勤時間を削減しました。さらに「活力朝礼」による凡事徹底や「ありがとうカード」でのコミュニケーション強化、年2回の教育受講義務化など人間磨き教育を徹底。これらの取り組みにより労働時間は大幅減少したものの収益は維持し、5年連続で健康経営優良法人認定を受けています。
出典:厚生労働省働き方改革特設サイト 中小企業の取り組み事例, 参照日2025年5月28日
残業削減の注意点
残業削減を進める際の注意点を解説します。ポイントを押さえて効果的な残業削減を進めましょう。
業務プロセスの改善なき残業削減は逆効果
残業時間の削減だけを目的にすると、サービス残業であったり、急いで業務を行うあまりミスが多発したりするなど、かえって問題を悪化させる恐れがあります。残業削減は、業務量や業務プロセスの見直しと併せて実施しないと本末転倒の結果を招きかねません。
社員の声を無視した一方的な施策
会社や管理職から一方的に残業削減施策を押し付けると、社員の反発を招き、想定した効果が得られない恐れがあります。社員の声を聞きながら、現場の実情に合った施策を立案・実施することが、持続的な残業削減の鍵となります。
管理職の意識改革
残業削減を進める上で鍵となるのが管理職の意識改革です。「残業=頑張っている」という古い価値観を持つ管理職が評価者である場合、いくら制度を整えても残業削減は進みません。管理職への研修や、管理職自身の働き方の見直しなど、上からの意識改革も重要です。
収入減に対する不安への配慮
残業時間が減ると残業代も減少するため、社員の収入低下にもつながります。人事制度そのものや基本給の見直し、業績に連動した特別ボーナスの支給など、収入面での配慮も検討する必要があります。
隠れて残業をすることを防止
「サービス残業」や「持ち帰り残業」などの隠れ残業を防止する対策も必要です。これらを根本的に解決するには、社員自身の意識改革も重要となります。「残業しないと評価されない」といった意識を変えるため、全社的な働き方改革の意識浸透や、業務量や負担などを相談しやすい風通しの良い職場づくりが求められます。
業務改善と制度見直しで効果的な残業削減が可能
残業削減は単に労働時間を減らすだけの問題ではなく、企業の生産性向上と社員のワークライフバランス実現という両面から取り組むべき重要な経営課題です。残業を減らすには「残業が発生する本質的な原因の特定」と「それに対応した効果的な対策の実施」が不可欠です。業務プロセスの見直しや勤怠管理の可視化、評価制度の改革など、複数の施策を組み合わせることで、より大きな効果が期待できます。
DBJデジタルでは、業務改善コンサルティングを通じて企業の生産性向上を支援しており、残業削減にも貢献します。業務プロセスの最適化や効率化に関するご相談は、お気軽にDBJデジタルにお問い合わせください。
 リクルート
リクルート ダウンロード
ダウンロード