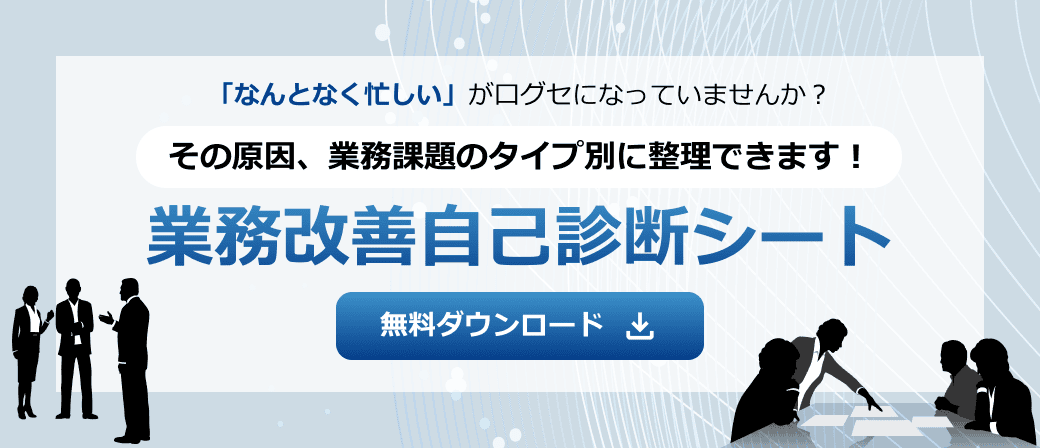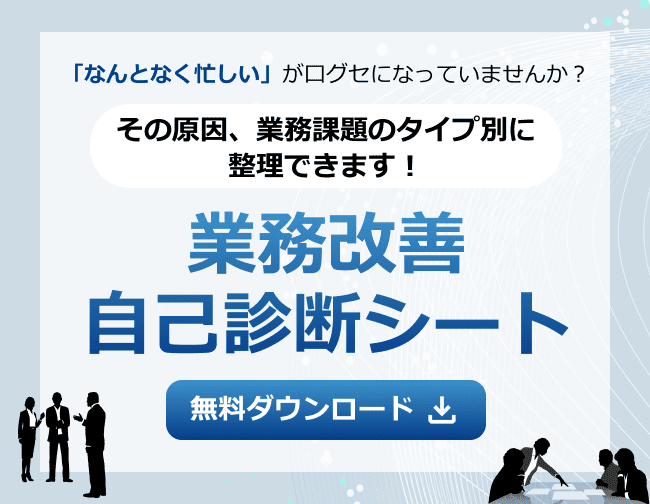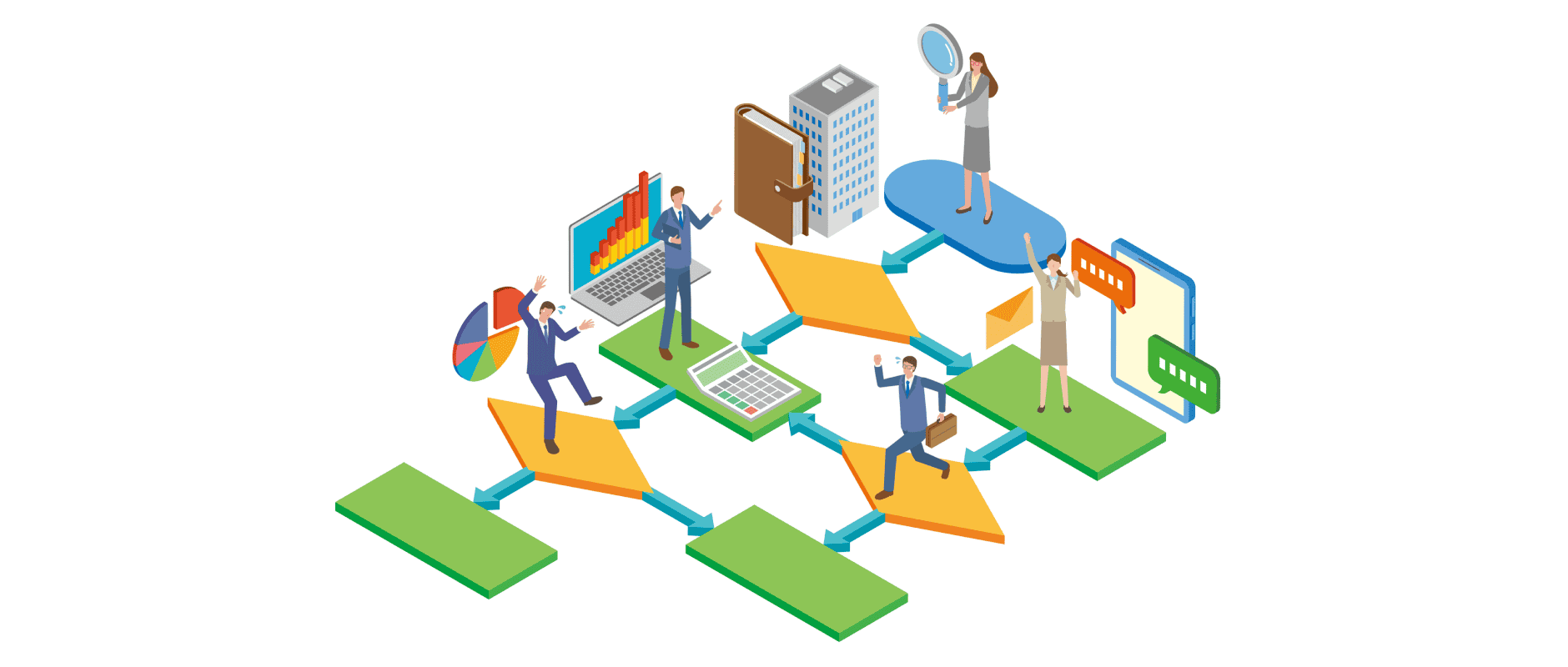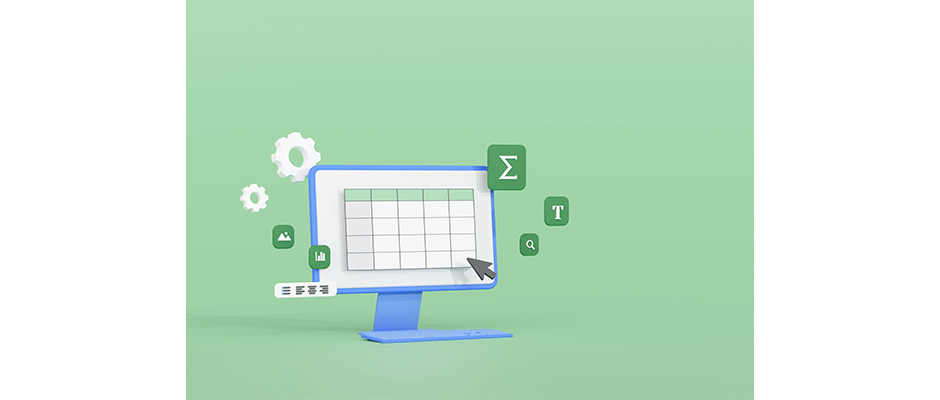業務改善が失敗する5つの原因を解説|問題点がわかるチェックリストつき
2025.07.12

多くの企業が業務効率化や生産性向上を目指して業務改善に取り組んでいますが、せっかく時間とリソースを投入しても効果が得られない、それどころか失敗に陥るケースも珍しくありません。本コラムでは、業務改善が失敗する主な原因と、成功に導くための具体的なアプローチについて解説します。また業務改善を行うにあたって、実施前~実施後の各段階で行うべきチェックリストも用意しているため、ぜひご活用ください。
業務改善が失敗する5つの原因
まずは業務改善プロジェクトが失敗する原因について解説します。
【現状分析】業務フローの可視化とボトルネックの特定ができていない
業務改善で失敗する多くの企業では、業務改善を始める前に十分な現状分析を行わないまま対策を講じようとします。しかし、業務の流れを正確に把握し、どこにボトルネックや無駄が存在するのかを特定することなく進める改善は、的外れな対策になりがちです。
特に既存業務の実態を詳細に把握せずに「とりあえず効率化」を進めようとするケースでは、現場部門の混乱を招き、かえって生産性が低下することもあります。
【組織運営】トップから現場への一方的な指示で改善を押し付けている
業務改善の取り組みが、経営層やプロジェクトチームからの一方的な指示で進められると、現場部門の反発や無関心を招きやすくなります。
現場の理解を得ないまま改革を押し進めると、「また上からの無理難題」と捉えられて協力が得られず、せっかくの取り組みも形骸化してしまいます。一方で、強力なリーダーシップがなければ進まない改善もあるため、トップダウンの推進力とボトムアップとなる現場部門の理解・参画のバランスが重要です。
【ツール選択】現場の実態に合わないシステムやツールを導入した
業務改善のためにシステムやツールを導入する際、「最新だから」「他社が使っているから」といった理由で選定してしまうことがあります。しかし、自社の業務課題や現場の実情に合っていないツールを導入しても、効果は期待できません。また、導入後のサポート体制が不十分な場合も、高額なシステム投資を活かしきれない原因となります。
【目標設定】目標が抽象的で具体性に欠けている
業務改善の取り組みでよく見られるのが、「業務の効率化を図る」「生産性を向上させる」といった抽象的な目標設定です。このような曖昧な目標では、何をどこまで改善すれば成功なのか判断できず、関係者の意識共有も難しくなります。また、成果測定の基準も不明確になるため、取り組みの途中で方向性を見失ったり、改善の効果を適切に評価できなかったりする問題も生じます。
【運用管理】新しいシステム導入後のサポートなく現場に任せきりにする
新しいシステムやプロセスを導入した後、十分なフォローアップなしに現場部門に丸投げしてしまうケースも多く見られます。「導入して終わり」では、使い方の疑問や運用上のトラブルに現場部門が対応できず、次第に旧来のやり方に戻ってしまいます。
失敗から学ぶ業務改善のユースケース
次に、業務改善が失敗するケースとその教訓を具体例も交えて紹介します。これらの失敗事例から学び、同様の問題を避けるための対策を押さえましょう。
【小売業界】在庫管理システム導入の失敗と対策
全国展開するアパレルチェーン企業では、在庫問題解決のために在庫管理システムを導入しましたが、スタッフの入力ミスが多発し、在庫データの信頼性が低下。かえって在庫問題が悪化してしまいました。導入後、現場部門の意見を取り入れずに選定したため、操作が業務に適合していないことが判明しました。
- 店舗スタッフのITリテラシーに大きな差があったにもかかわらず、研修は一度しか実施しなかった
- 導入後のサポートやフォローはなく運用は現場部門任せであった
- 新システムが店舗の業務フローに合っておらず、作業負担が増加した
- 店舗の繁閑に配慮しない、日常業務に支障をきたすシステム設計であった
【業務改善が失敗した理由】
この失敗を避けるには、導入前に現場スタッフを交えたシステム選定、操作研修の徹底、導入初期の手厚いサポート体制構築が必要となります。この事例から、システム選定時には実際の利用者の能力や業務実態に合わせたユーザビリティの検討が不可欠であること、そして導入後も継続的なサポートと改善が必要だという教訓が得られます。
【金融業界】電子申請システム導入の失敗と教訓
ある地方銀行では、個人ローン申込手続きの効率化のために電子申請システムを導入しました。しかし、既存の紙ベースの業務フローをそのまま残したため、紙と電子の二重管理が発生。かえって業務負担が増え、処理時間の短縮効果は限定的でした。
- 「万が一のため」という理由で紙の申込書と審査書類も並行保管する設計であった
- 電子化に合わせた承認プロセスの簡素化を行わなかった
- 新旧システムの並存による二重作業の発生を軽視した
- 同じ情報を紙と電子の両方に記録する、非効率な運用体制が生じた
【業務改善が失敗した理由】
この失敗から学べる教訓は、新システム導入前に業務フロー全体の見直しが必須であること。紙ベースプロセスの完全廃止、承認ステップの簡素化、情報管理の一元化(電子システムへの完全移行)が必要ということです。業務改善の本質は「システム導入」ではなく「プロセス改革」にあるという重要な気づきがこの事例から得られます。
【保険業界】営業支援システム刷新の迷走
大手生命保険会社では、営業職員の活動効率化を目的に営業支援システムを全面刷新しました。しかし、新システムの利用率は予想を大きく下回り、導入から1年経過しても半数以上の営業職員が従来の方法で顧客管理を続ける事態に陥りました。
- 現場営業職員の意見聴取が不十分だった
- 平均年齢が高い営業組織の特性を考慮していなかった
- モバイル環境での使いづらさが顕著だった
- システム導入の目的や効果の共有が不足していた
【業務改善が失敗した理由】
この失敗事例からは、システム開発においてはエンドユーザーである現場担当者の実態把握が最重要であること、特に年齢層や働き方の多様性を考慮したデザインが必要であることがわかります。また、システム導入の目的や期待される効果を丁寧に説明し、現場の協力を得ることが成功の鍵となります。
業務改善を成功させる方法
前章で見てきた失敗原因や事例を踏まえ、業務改善を成功させるための具体的な方法を解説します。
【現状分析】実際の業務プロセスを見える化して問題点を洗い出す
業務の棚卸しを行い、業務フロー図やプロセスマップを作成して「誰が、何を、いつ、どのように行っているのか」を明確にします。この分析には、実際に業務を行っている現場部門の参加が欠かせません。
特に重要なのは、表面的な業務フローだけでなく、「なぜそのように行っているのか」という背景や理由まで深掘りすることです。業務の中に潜む無駄や非効率の根本原因を特定できれば、的確な改善策を講じることができます。また、業務量調査を実施して定量的なデータを収集することも、客観的な現状把握には効果的です。
業務の棚卸や業務課題に関して詳しくは以下もご覧ください。
【組織運営】現場の声を取り入れた全員参加型の改善活動を推進する
業務改善を成功させるためには、トップダウンとボトムアップのバランスが重要です。経営層のコミットメントと方向性の提示に加えて、実際に業務を行う現場部門の声を積極的に取り入れる体制づくりが必要です。
そのためプロジェクトの初期段階から現場部門を参画させて、改善の必要性や目的を共有することで当事者意識を高めます。また、改善活動の進捗や成果を定期的に全社で共有し、小さな成功体験を積み重ねていくことで、組織全体の改善マインドを醸成していくことが大切です。現場部門の抵抗感を和らげるために、「これまでの仕事を否定するのではなく、さらに価値を高めるための取り組み」というポジティブなメッセージを発信し続けることも欠かせません。
【ツール選択】解決すべき課題に最適なシステムやツールを見極める
業務改善のためのシステムやツールを選定する際は、まず解決すべき課題を明確にし、それに最適なソリューションを選定するという視点が重要です。選定のポイントとしては、自社の業務規模や特性への適合性、必要機能の充足度、使いやすさ、既存システムとの連携性、コストなどを検討することが大切です。コスト捻出が難しい場合はEUCの導入が有効です。また、一度に全てを変えるのではなく、小規模な試験導入から始めて段階的に拡大していく方法も効果的です。
EUCに関して詳しくは「EUCとは?業務効率化を実現する仕組みと導入ステップを解説」もご覧ください。
【目標設定】数値化できる具体的な目標と達成基準を明確にする
目標設定の際には、SMART基準(Specific:具体的、Measurable:測定可能、Achievable:達成可能、Relevant:関連性がある、Time-bound:期限がある)を活用すると効果的です。また、目標設定の際には、会社全体の方針や戦略との整合性も明確にしておくことが大切です。
例えば「生産性向上」という抽象的な目標ではなく、「受注処理時間を3カ月以内に30%削減する」「入力ミスによる再作業を半年で80%削減する」など、具体的な数値と期限を含む目標を設定しましょう。また、目標達成によって得られるメリットを金額や時間などの具体的な価値に換算して示すことで、関係者の理解と協力を得やすくなります。
【運用管理】継続的なフォローと効果測定で定着を図る仕組みを作る
専門のサポートチームを設置する、定期的な研修やQ&Aセッションを開催する、問い合わせ窓口を設けるなどの対応が重要です。特に導入初期は手厚いサポート体制を整え、利用者の不安や疑問へ素早く対応することが重要です。また、定期的に振り返りミーティングを開催し、新しい業務プロセスやシステムの課題を洗い出して改善していくPDCAサイクルを確立することで、持続的な改善ができます。
また、成果の見える化のため、導入前に設定した目標に対する達成度を定期的にチェックする効果測定の仕組みも導入し、改善取組みの定着化を図りましょう。
業務改善を成功に導くためのチェックリスト
業務改善を行う際に、各段階で確認すべき重要項目をまとめました。このチェックリストを活用して事前準備の不足点を把握し、効果的な改善活動を実現しましょう。
【計画段階】プロジェクトの基盤を固めるチェックポイント
- □ 現状の業務フローと問題点が可視化されているか
- □ 現場部門の声を取り入れる仕組みがあるか
- □ 経営層のコミットメントと必要なリソースが確保されているか
- □ 具体的な数値目標と達成期限が設定されているか
- □ 改善効果を測定する指標と方法が明確になっているか
【実施段階】円滑な導入を確保するチェックポイント
- □ 段階的な導入計画が立てられているか
- □ 十分な研修とマニュアルが準備されているか
- □ 導入初期のサポート体制は整備されているか
- □ 問題発生時の対応フローが明確になっているか
- □ 現場からのフィードバックを収集する仕組みがあるか
【評価・改善段階】持続的な効果を確保するチェックポイント
- □ 定期的な効果測定と目標達成度の確認が行われているか
- □ 新たな問題点や改善機会の洗い出しが継続されているか
- □ 好事例の共有と水平展開が行われているか
- □ 関係者への適切なフィードバックと評価が行われているか
- □ 長期的な改善計画が策定されているか
チェックがつかなかった所が、業務改善を推進する際の問題点となります。全項目にチェックがつくことで、プロジェクトの成功率が向上します。
業務改善の具体的な施策に関しては以下もご覧ください。
業務改善の失敗を避けるには計画・実行・評価の段階を踏んで実践することが重要
業務改善の失敗は、推進にあたっての知識・経験の欠如や準備不足といった要因が考えられます。成功のためには、明確な計画立案と目標設定、業務プロセスの可視化、そして継続的なサポート体制の構築が必要です。
一方で、専門知識や経験がなければ難しい取り組みでもあります。業務改善でお悩みの際は、豊富な実績と専門ノウハウを持つDBJデジタルにご相談ください。
 リクルート
リクルート ダウンロード
ダウンロード