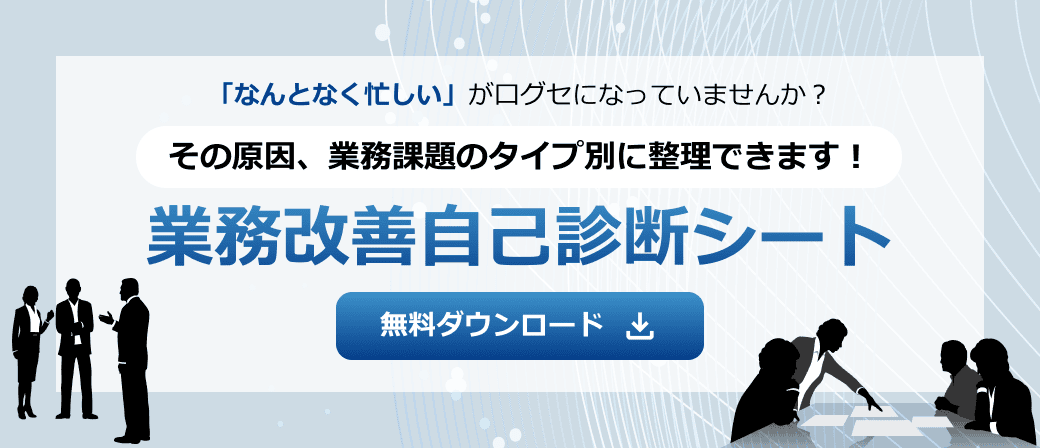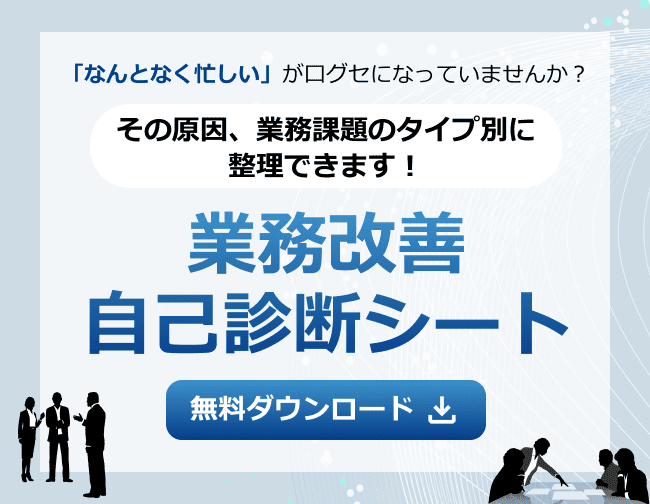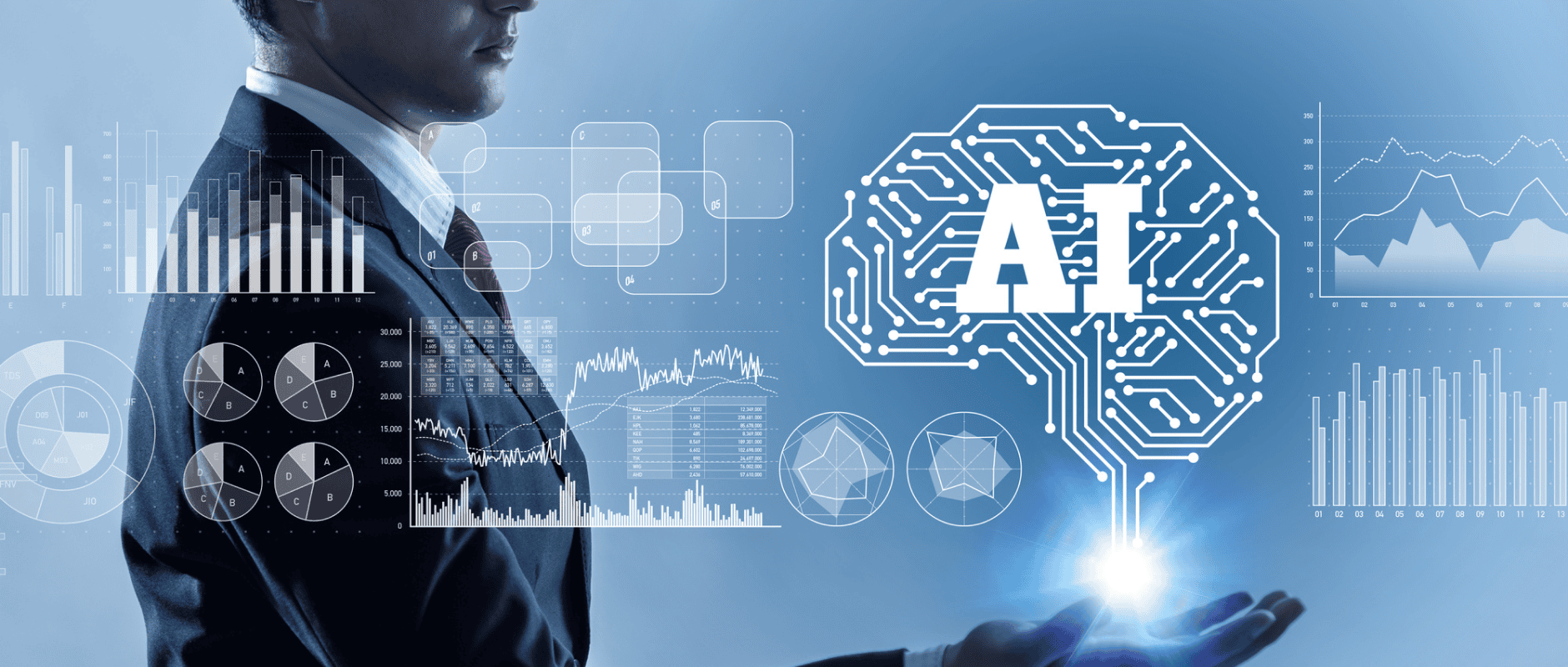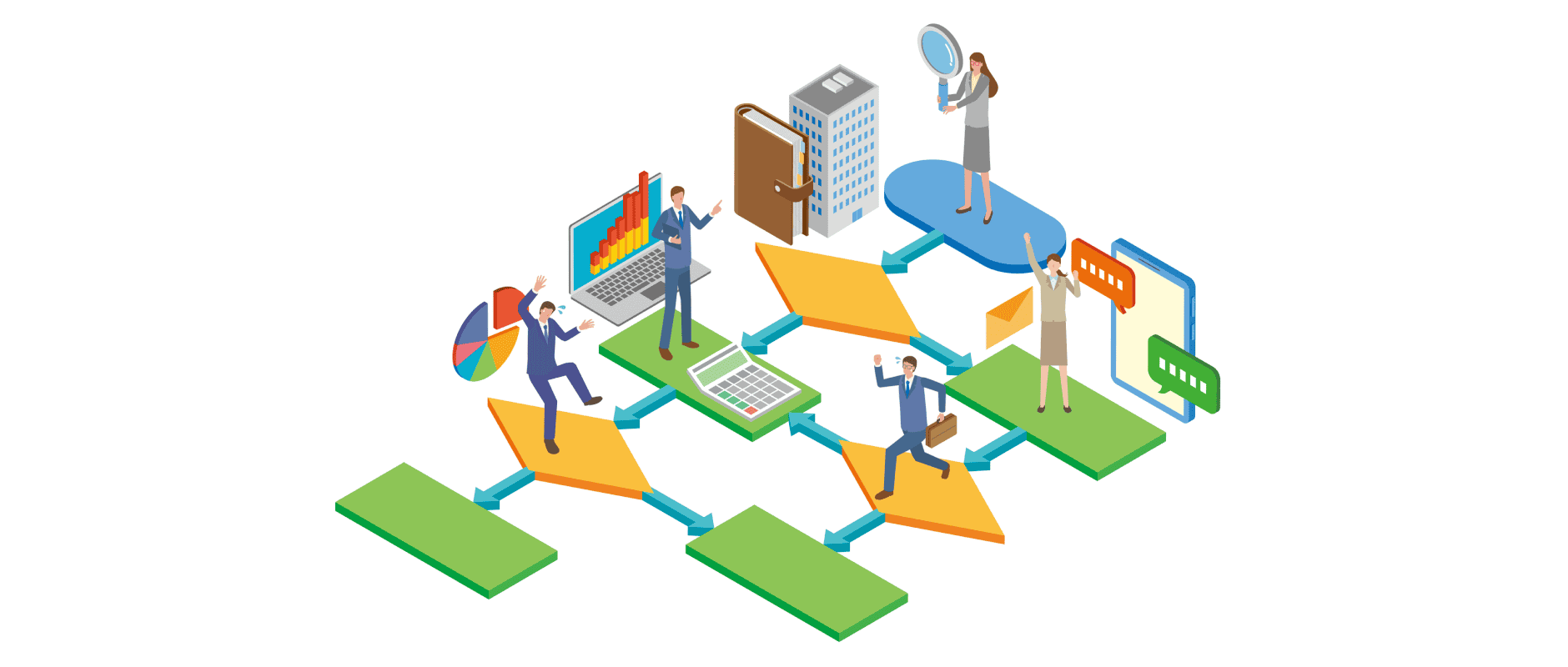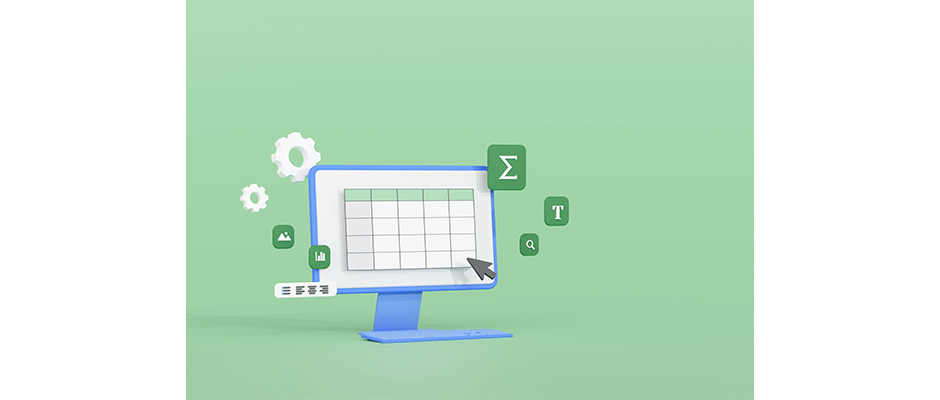業務課題とは?可視化の方法から解決手順までを解説
2025.05.01

業務改善を行うにあたって、業務課題の特定が改善活動の第一歩となります。しかし、「課題が多すぎて整理できない」「本質的な課題が見えない」という声をよく耳にします。本コラムでは、多くの企業で見られる代表的な業務課題とその解決方法、さらに改善がもたらす具体的なメリットについて解説します。
業務課題とは?
業務課題とは、業務の効率性や生産性を低下させる要因のことを指します。多くの企業では、日々の業務に追われるあまり、こうした課題に対して「何となく効率が悪いと感じている」という状態で放置されがちです。しかし、実際にはミスの発生や社員の残業時間増加、さらには人材の離職にまでつながる重要な経営課題となっています。
業務課題の3つの性質と具体例
業務課題は、その性質によって「発生型」「潜在型」「設定型」の3つに分類できます。それぞれの特徴を理解することで、自社が直面している課題をより正確に把握し、適切な対応を取ることができます。
発生型の業務課題
発生型の業務課題とは、すでに顕在化して目に見える形で現れている問題です。即座の対応が求められ、放置すると業績や社員のモチベーションに直接的な影響を及ぼします。具体的には以下のような課題が挙げられます。
- 恒常的な残業
- 業務上のミスの頻発
- 顧客からのクレーム
- データの重複入力による非効率
発生型の課題は、組織にとって「喫緊の経営課題」として認識されるため、対応への理解が得やすいことが特徴です。一方で、対症療法的な対応に終始すると根本的な解決にならないケースも多いため注意が必要です。例えば、ミスが発生するたびに確認作業を増やすといった対応は短期的にはミス防止に効果がありますが、長期的に見ると業務負荷が増加することで別の問題を生み出す可能性があります。発生型の課題に対しては、「なぜそれが起きるのか」という根本原因を特定し、プロセス自体を見直すアプローチが効果的です。
潜在型の業務課題
潜在型の業務課題は、現時点では大きな問題となっていないものの、将来的なリスクとして認識すべき課題です。具体的には以下のような課題が挙げられます。
- 業務の属人化リスク
- マニュアルの未整備
- システムの老朽化
- スキル継承の遅れ
潜在型の課題は、「見えない問題」であるがゆえに対応が後回しにされがちです。しかし、トラブルや退職といったイレギュラーな危機に直面した際に組織の脆弱性として顕在化します。例えば、特定の業務が一人に依存している状態(属人化)は、その担当者が突然の離職や長期の病欠となった場合、業務の停滞や品質低下といった問題を引き起こします。こうした見えないリスクに対しては、「もし発生したらどれだけ影響があるか」と「実際に起こる確率はどれくらいか」を定期的に検討し、重要度の高い課題から対応していくことが大切です。
属人化の解消に関して詳しくは「属人化解消の具体的な進め方|リスク分析から効果的な対策まで」もご覧ください。
設定型の業務課題
設定型の業務課題は、組織として積極的に取り組むべき改善テーマです。具体的には以下のような課題が挙げられます。
- 業務プロセスの標準化
- システム化による効率化
- 部門間連携の強化
- コスト構造の改善
設定型の課題は、現状の問題解決というよりも、将来を見据えた組織の競争力強化や成長に向けた「投資」としての側面を持ちます。例えば、業務プロセスの標準化は短期的には手間がかかりますが、長期的には品質の安定化や人材の配置にも柔軟に行えるようになるため、継続的改善の基盤となります。また、DX(デジタルトランスフォーメーション)などの戦略的な取り組みも、この設定型の課題に含まれます。これらの課題に対しては、経営戦略との整合性を確認しながら、中長期的な視点で計画的に取り組むことが重要です。投資対効果を評価しつつ、段階的に実施していくことが成功の鍵となるでしょう。
これら3つの性質を持つ業務課題を適切に特定するためには、まず現状を客観的に「見える化」(可視化)する必要があります。
業務課題を可視化する4つの方法
業務課題の本質を理解するためには、まず現状を「見える化」する必要があります。ここでは、効果的な4つのアプローチ方法をご紹介します。
業務プロセスを可視化し非効率な作業を特定する
業務フロー図を作成することで、業務の流れ・プロセスを視覚的に把握できます。例えば、ある企業の人事部門では、入社手続きの業務フロー図を作成したところ、同じような書類確認が3ヶ所で行われていることが判明しました。これにより、確認プロセスの統合という具体的な改善点が明確になりました。
作業時間を計測して負荷を把握する
ワークサンプリング法を用いて、業務時間の分布を測定します。この手法では、一定の時間間隔(例えば15分ごと、1時間ごとなど)で定期的に「その時点で行っている作業」を記録し、各業務に費やされる時間の割合を統計的に把握します。十分なサンプル数を確保することで、業務全体における時間配分の傾向を定量的に分析できます。例えば「データ入力作業が全体の25%を占める」「会議が15%」といった形で、業務負荷の分布を客観的に可視化できます。業務量を調査することで、改善点の優先順位をつける判断材料となります。
業務量調査に関して詳しくは「業務量調査とは?3つの方法と業務改善への活用ポイントを具体例付で解説」もご覧ください。
社員の声からボトルネックを特定する
現場社員へのヒアリングは、定量的な数値では見えない定性的な課題を発見するのに効果的です。ただし、「忙しい」「大変」といった抽象的な声に終始しないよう、具体的な状況や頻度を確認することが重要です。「いつ、どのような状況で問題が発生するか」を具体的に質問することで、表面的な不満ではなく、本質的な課題を特定できます。
部門をまたぐ課題を共有する
部門間の業務の流れを業務関連図(クロスファンクショナルマップ)として図式化します。例えば、受注から納品までの一連の流れを図にすることで、「営業部門の提案資料作成が遅れると、製造部門の生産計画に影響が出る」といった部門間の相互依存関係が明確になります。特に、情報の受け渡しや承認プロセスなど、部門間での連携が必要な箇所でどのような課題が発生しているかを、関係者間で共有・議論することができます。
効果的な課題解決のステップ
課題が明確になったら、次は解決に向けたアプローチを検討します。ここでは、成功率を高めるための3つのステップを解説します。
現状業務の可視化と分析
まず、現状の業務フローを詳細に分析します。各工程の所要時間、担当者、必要書類、使用システムなどを洗い出し、業務の全体像を「見える化」します。この段階では以下の方法が有効です。
- 業務フロー図を作成して全体像を把握
- 業務量調査を実施して各工程の時間を定量的に分析
またこの際に業務の棚卸しも行うことで、無駄な工程や改善点を発見にもつながります。
業務の棚卸しに関して詳しくは「業務の棚卸しの進め方|5つの手法と実践ステップを解説」もご覧ください。
優先順位の決定方法
すべての課題を一度に解決することは困難です。「実現難易度」と「期待効果」の2軸でマッピングし、優先順位を決定します。特に、すぐに着手できて効果の高い「Quick Win」から着手することで、改善機運を高めることができます。現場社員へのヒアリングと業務量調査のデータを組み合わせて、優先度の高い課題を特定しましょう。
解決策の立案と実行計画
具体的な解決策を検討する際は、以下の3つの視点を意識します。
- 業務プロセスの最適化
- システムによる自動化
- 人材育成とナレッジ共有
検討した解決策は、短期・中期・長期の時間軸で整理し、実行計画を立てることが重要です。各施策に対して「いつまでに」「誰が」「何を」実施するかを明確にし、担当者と期限を設定します。また、成功基準となるKPIを設定し、定期的に進捗を確認する仕組みを作ることで、PDCAサイクルを回しながら継続的な改善を実現できます。
業種や部門によって効果的な改善施策は異なりますが、汎用的に活用できる実践的なアイデアも多くあります。
改善施策に関しては「業務改善アイデア15選!部門別の改善施策を具体的に紹介」もご覧ください。
課題解決を成功に導くポイント
最後に、業務課題の解決を成功させるためのポイントをご説明します。
定量的な目標設定
課題解決の成否を判断するためには、定量的な指標を設定しましょう。例えば、「処理時間の30%削減」「エラー率の50%低減」といった具体的な目標を設定することで、改善の効果を客観的に評価できます。
効果的なツール選定
業務効率化を実現するためには、課題別に適したツールを積極的に活用しましょう。特に、EUC(End User Computing)ツールは、現場主導での業務改善を可能にする強力な味方となります。
EUCに関して詳しくは「EUCとは?業務効率化を実現する仕組みと導入ステップを解説」もご覧ください。
段階的な改善アプローチ
大きな改革は、一度に行うのではなく、段階的に進めることが成功の鍵です。例えば、ある保険会社ではまず保険金請求書のチェックフロー整備と標準化から着手して、書類不備による差し戻し率を大きく削減しました。この成功体験が社員の改善に対するモチベーションを高め、次の改善ステップへとスムーズに進みました。このように、成功を積み重ねることで、組織全体の改善マインドを醸成できます。
業務課題の特定から改善まで、ステップを踏んで効率化を実現しよう
業務改善を成功させるには、発生型・潜在型・設定型という3つのタイプの課題を適切に把握し、優先順位をつけて取り組むことが重要です。業務の可視化から始まり、定量的な目標設定、適切なツール活用、そして段階的なアプローチによって、持続的な改善サイクルを構築していきましょう。小さな成功体験の積み重ねが、最終的には大きな組織変革につながります。
また業務課題の特定には、業務量調査が有効です。業務課題や業務量調査についてのご相談や、専門家による支援をご検討の場合は、お気軽にお問い合わせください。
 リクルート
リクルート ダウンロード
ダウンロード