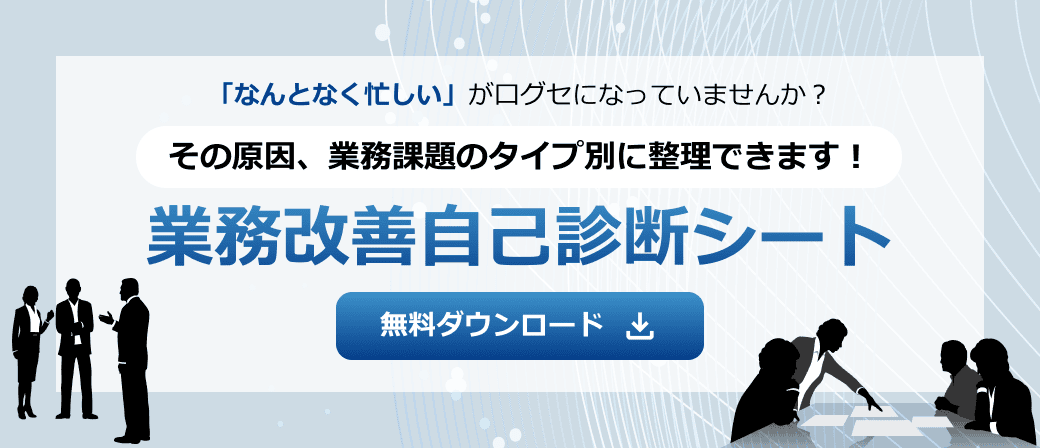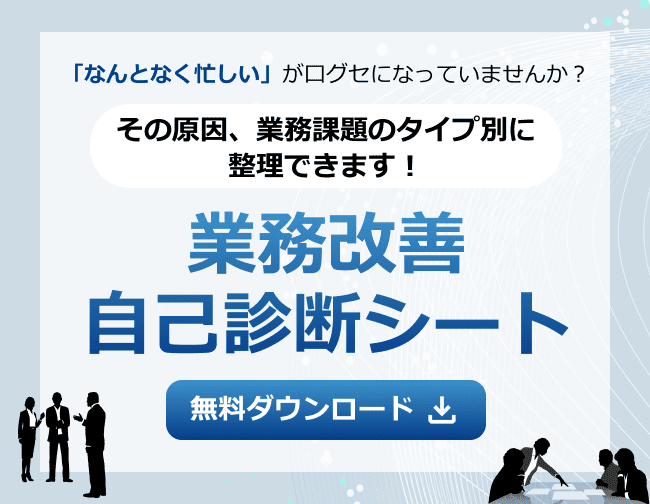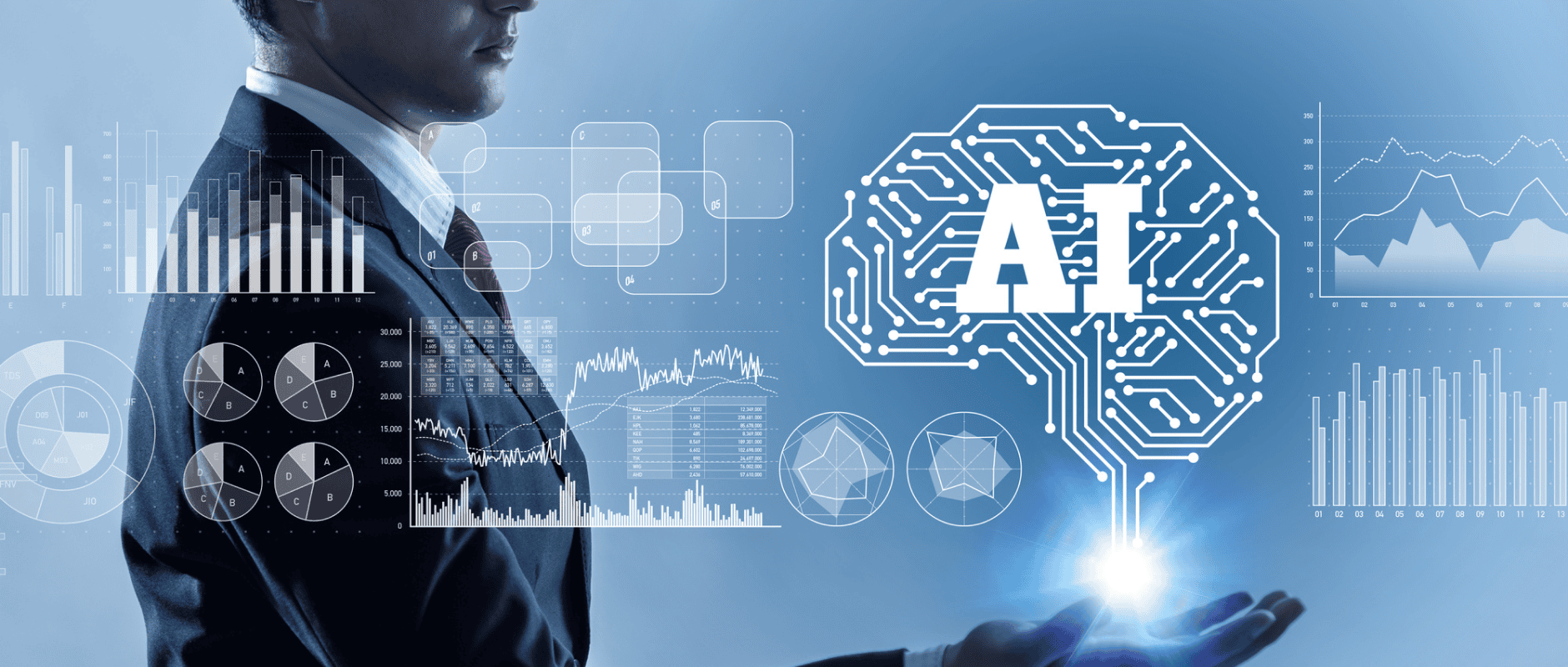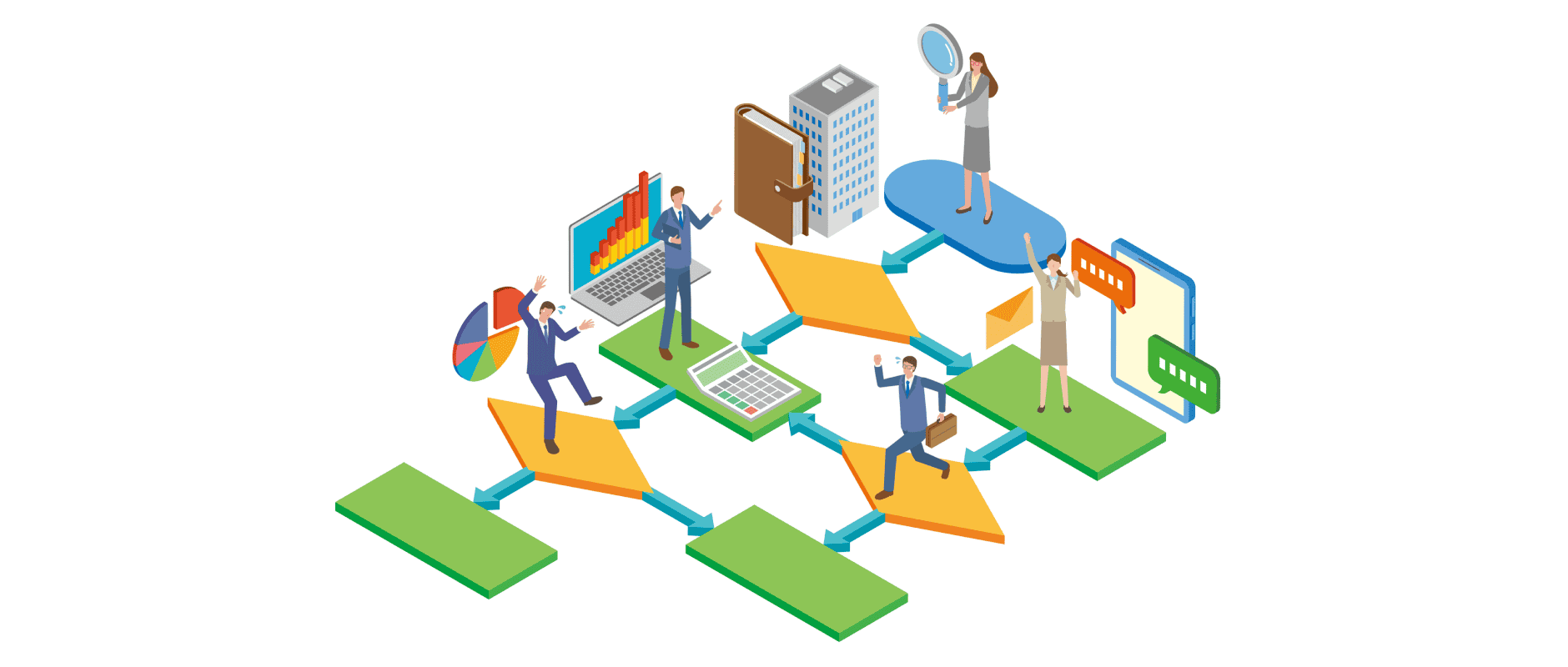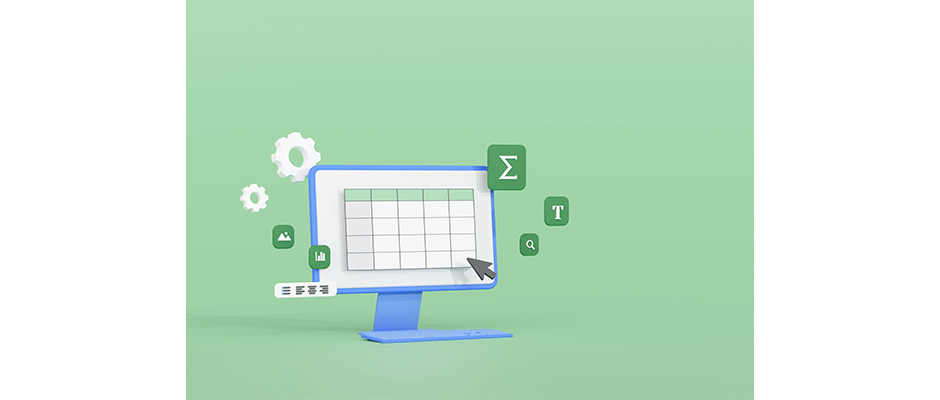属人化解消の具体的な進め方|リスク分析から効果的な対策まで
2025.02.21
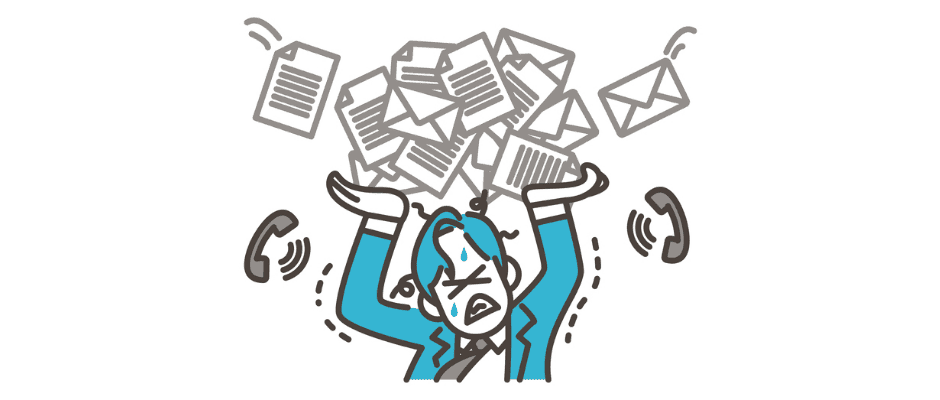
業務の現場では、特定の社員へ業務が集中したり、ベテラン担当者の退職リスクなど、属人化に関する問題が数多く発生しています。2021年の中小企業向け調査では、4社に1社が「業務知識の属人化」を人材育成の課題として挙げており、大企業でも同様の問題を抱えています。しかし、多くの企業では具体的な解決方法がわからず、対策が進んでいないのが現状です。本コラムでは、属人化解消の具体的な手順から、組織全体での取り組み方まで、実践的なノウハウをご紹介します。
属人化がもたらす4つのリスク
属人化は、組織の持続的な成長を脅かす深刻な問題です。具体的には、以下のようなリスクをもたらします。
1.業務の停滞・遅延リスク
特定の担当者が不在の際に業務が滞り、顧客対応や納期に支障をきたします。担当者自身も休暇取得も難しくなり、業務負担が増大する悪循環に陥ります。
2.品質管理の課題
標準化された手順やチェック体制が確立されていないため、成果物の品質にばらつきが生じやすく、ミスの発見も遅れがちです。特に複雑な判断が必要な業務や、複数のシステムを使用する業務では、担当者によって処理方法が異なり、結果に差が出る恐れもあります。
3.事業継続の危機
核となる人材が退職した際、重要なノウハウや取引先との関係性が失われ、組織に致命的なダメージを与える可能性があります。特に、主要取引先とのやり取りや、システムの保守運用など、長年の経験と知識が必要な業務では、その影響も大きくなります。
4.組織成長の停滞
ノウハウの共有や改善活動が進まず、組織全体の生産性向上が妨げられます。若手社員の育成も滞りがちになり、組織全体のスキル向上や業務効率化の取り組みが進まない要因にもなります。
属人化が発生する原因とは
以下の4つの要因が複雑に絡み合って、属人化は進行していきます。
短期的な効率性重視
「この人に任せた方が早い」という判断の積み重ねが、特定の担当者への業務集中を引き起こします。例えば、急ぎの案件が発生した際に「教える時間がない」という理由で、いつも同じ担当者に依頼してしまうケースがこれに当たります。
マニュアル化が不十分
業務手順やノウハウの文書化が不足したまま、OJTによる技能伝承が続くことで、「暗黙知」が蓄積されていきます。特に、ベテラン社員の持つ経験則や判断基準は、文書化されないまま属人的なノウハウとして蓄積されがちです。
組織文化の影響
「自分にしかできない仕事を持つことが評価につながる」という認識が、意図的な属人化を助長することがあります。「自分の専門分野を持つことは良いこと」という考えが、必要以上の属人化を招いているケースもあります。
人材育成の軽視
人手不足や短期的な利益追求により、新人教育や複数担当者の育成といった将来への投資が後回しにされがちです。「今は忙しいから」と教育の機会を逃し続けることで、結果的に属人化が固定化されてしまいます。
属人化の解消によるメリット
属人化を解消する具体的なメリットは、前述した4つのリスクの低減です。業務の停滞・遅延リスクが解消されることや、標準化された手順とチェック体制で成果物の品質が安定化し、ミスの早期発見も可能になります。
さらに、以下の効果も期待できます。
- 重要な人材が退職しても業務を継続できる
- 特定の社員への過度な負担が減り、退職リスクが下がる
- 若手社員が成長できる機会が増える
- 誰でも対応できる業務が増え、社員の配置が柔軟になる
- 特定の社員へ仕事が集中することが減り、残業削減につながる
- 組織全体の業務効率が上がり、会社の成長につながる
このように、属人化の解消は、個人の働き方改革から組織全体の成長まで、幅広い効果をもたらします。
属人化解消の具体的なステップ
属人化の解消を一度に行うことは難しいですが、計画的に進めることで確実に成果が出ます。以下の手順に沿って、一つずつ進めていきましょう。
Step1:現状分析と優先度設定
まず最初に行うべきは、属人化の現状を正確に把握することです。業務量を調査し、以下の2つの視点で分析を行います。
- 影響度評価:各業務の属人化がもたらすリスクを「業務の重要度」と「属人化の度合い」の2軸で評価します。例えば、売上に直結する業務や法定業務は重要度が高い。担当者が1名のみの業務は属人化度が高いと判断できます。
- リソース分析:誰がどの業務にどれだけの時間を費やしているかを定量的に把握します。これにより、特定の担当者への業務集中度が明確になります。
業務量調査に関して詳しくは「業務量調査とは?3つの方法と業務改善への活用ポイントを具体例付で解説」もご覧ください。
Step2:業務の可視化と分析
優先度の高い業務から、詳細な分析を進めていきます。例えば、売上への影響が大きい業務、法令順守に関わる業務などがあたります。
- 業務フローの作成:作業の流れ、判断基準、例外処理などを可視化します。この過程で、属人的な判断が必要な箇所や、効率化の余地がある部分が明確になります。
- 必要スキルの洗い出し:各業務に必要な知識やスキルを明確にします。「なぜその担当者しかできないのか」という理由を具体化することで、効果的な教育計画の立案につながります。
Step3:改善施策の立案と実行
分析結果を基に、具体的な改善施策を策定します。
- 短期的対策:まず、属人化のリスクを低減する緊急的な施策を実施します。例えば、バックアップ担当の設定や、最低限必要な手順書の作成などです。
- 中長期的対策:業務プロセスの再設計、システム化の検討、人材育成計画の立案など、恒久的な解決策を計画します。
| 対策区分 | 改善施策の立案(分析フェーズ) | 改善施策の実行(実行フェーズ) |
|---|---|---|
| 短期的対策 |
・バックアップ担当を設定する業務の特定 ・作成が必要な手順書の洗い出し ・緊急度の高い属人化業務のリストアップ |
・選定した業務へのバックアップ担当の配置開始 ・基本的な手順書の作成と運用 ・緊急性の高い属人化業務の改善着手 |
| 中長期的対策 |
・業務プロセス再設計の計画策定 ・導入検討が必要なシステムの選定 ・人材育成計画の立案 |
・新しい業務プロセスの段階的な導入 ・選定したシステムの導入と運用開始 ・策定した育成計画に基づく教育の実施 |
Step4:標準化・マニュアル化の実践
効果的な標準化のポイントは、以下の3つです。
- 視覚化の重視:フローチャート、チェックリスト、画面キャプチャなどを活用し、わかりやすい資料を作成します。特に例外処理や判断基準は、具体例を交えて説明することが重要です。
- 全体の流れを最初に作る:全体の流れを押さえた概要版を作成し、その後、必要に応じて詳細な手順書を追加していく方法が効果的です。
- 現場主体の定期的な見直し:作成したマニュアルは、実際の使用状況を踏まえて改訂を重ねていきます。現場が主体的にブラッシュアップすることで、より実用的な内容に進化させていきます。効率的かつ、現場の意識改革にもつながります。
Step5:EUCを導入する
EUCは属人化解消の有効なツールとなります。一方で、以下のようなルールを整備して統制管理を行いましょう。
- 開発ガイドラインの整備:命名規則、開発手順、テスト方法など、基本的なルールを定めます。これにより、他のメンバーによる保守や改修が容易になります。
- 文書化の徹底:仕様書やマニュアルの作成を必須とし、開発者以外でも運用できる状態を確保します。
- 共有と承継の仕組み:定期的な勉強会やナレッジ共有の場を設け、EUCの活用ノウハウを組織全体に広めていきます。
- EUC統制の整備:開発・運用・保守に関する管理体制を確立し、リスクの低減と品質の確保を図ります。
以上のステップを着実に実行することで、効果的に属人化を解消できます。特に重要なのは、「急がば回れ」の精神です。
EUCに関して詳しくは「EUCとは?業務効率化を実現する仕組みと導入ステップを解説」もご覧ください。
◆ DBJデジタルの『業務Analyze』ならば、業務の可視化から改善施策の提案を行い、経験豊富な専門家が一気通貫でサポートいたします。
通常業務を妨げることなく、作業レベルまで踏み込んで詳細な業務把握が行うことが可能です。可視化されたデータを元に、業務プロセスの見直しやシステム改善施策の提案など、効果的な課題解決をアプローチします。詳細や興味をお持ちの方はお気軽にお問い合わせください。
業務Analyze:https://www.dbj-digital.jp/service/consulting/euc/analyze/
属人化解消は、リスク分析から始める。組織全体で取り組む継続的な改善が成功の鍵
属人化の解消は、一朝一夕には実現できません。しかし、本コラムでご紹介した手順に従って着実に取り組むことで、必ず成果につながります。まずは自社の状況を正確に把握し、優先度の高い業務から段階的に対策していきましょう。より詳細な属人化対策の進め方や、プロフェッショナルによる支援をご検討の際は、ぜひDBJデジタルソリューションズにお問い合わせください。
 リクルート
リクルート ダウンロード
ダウンロード