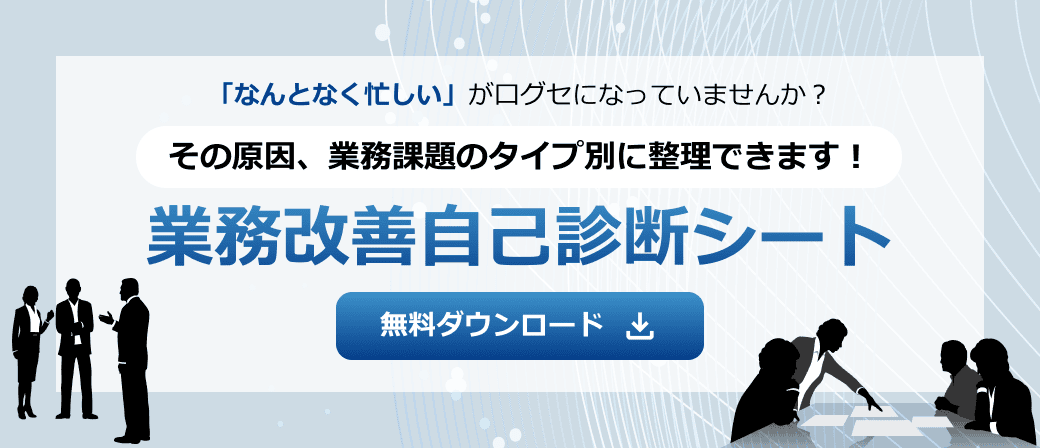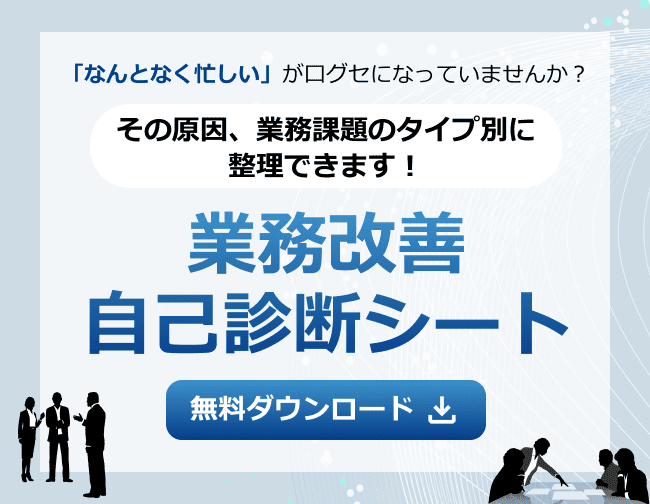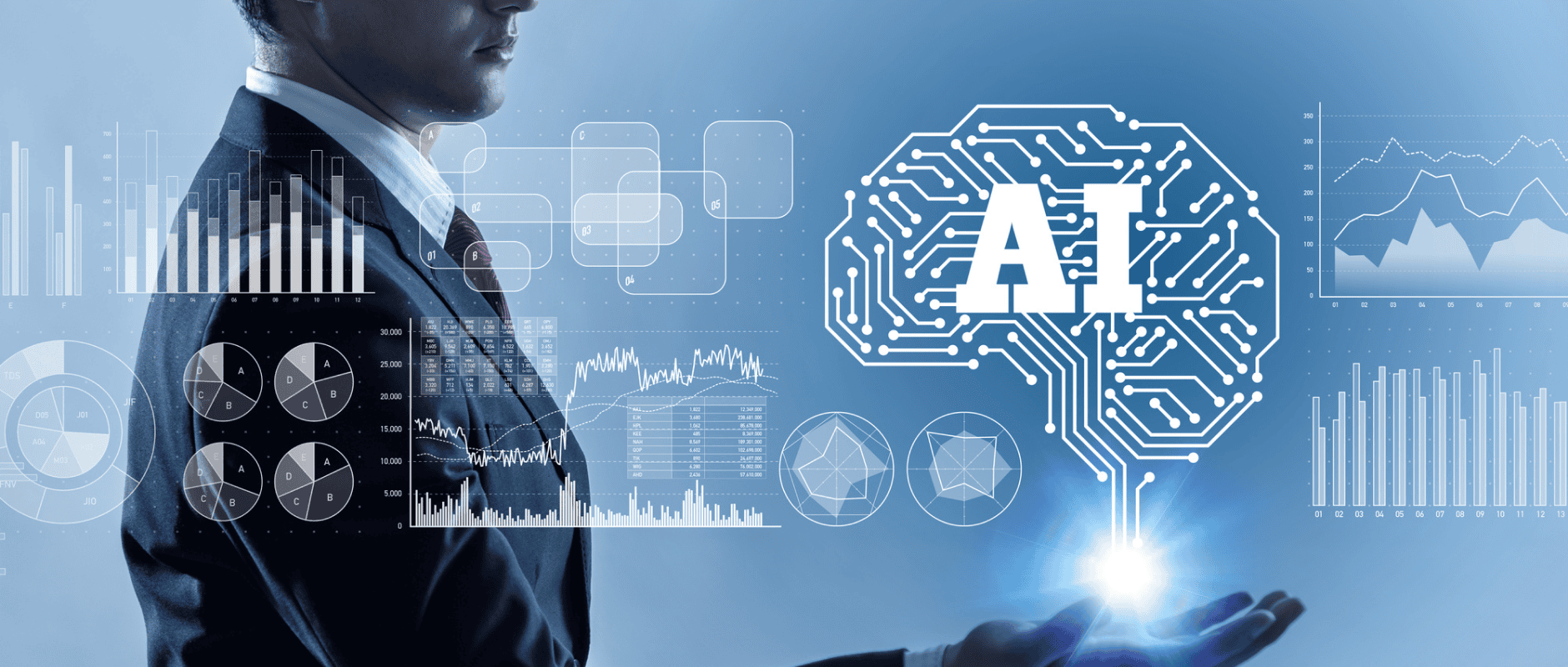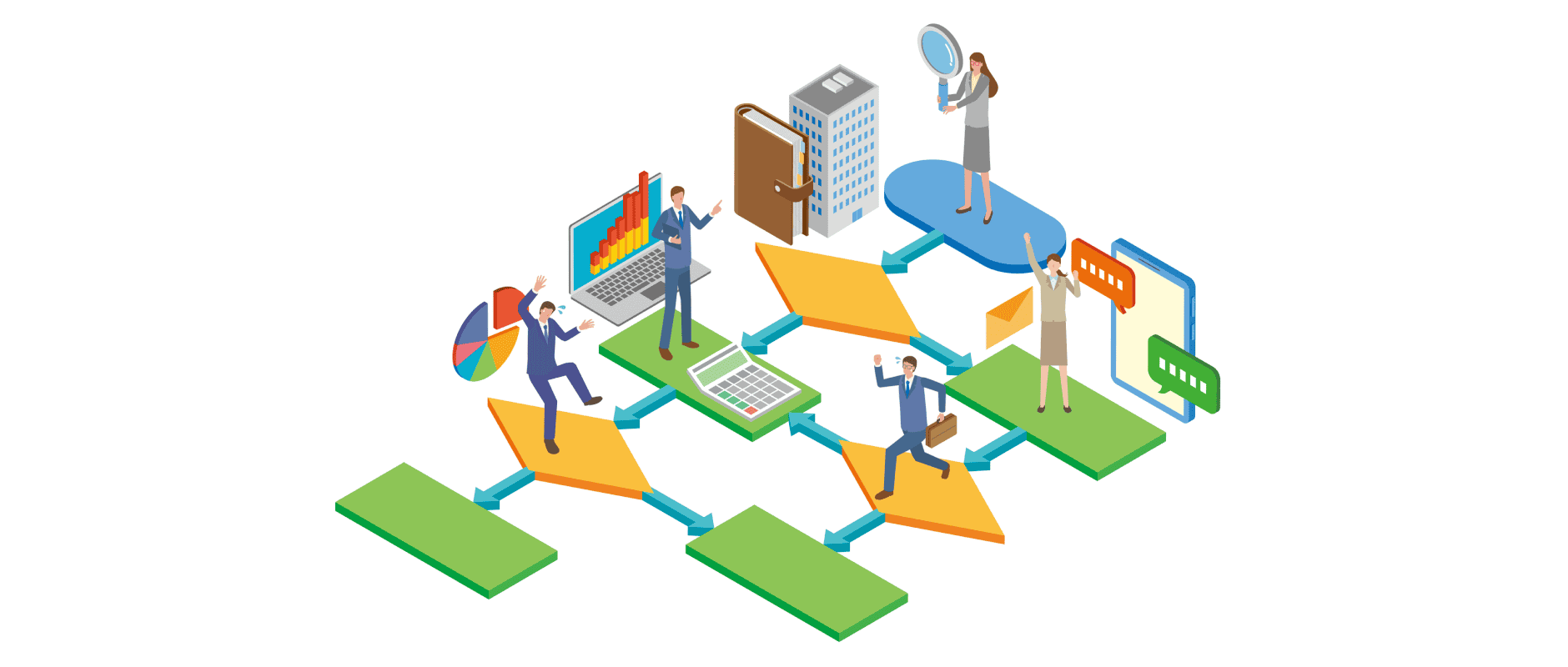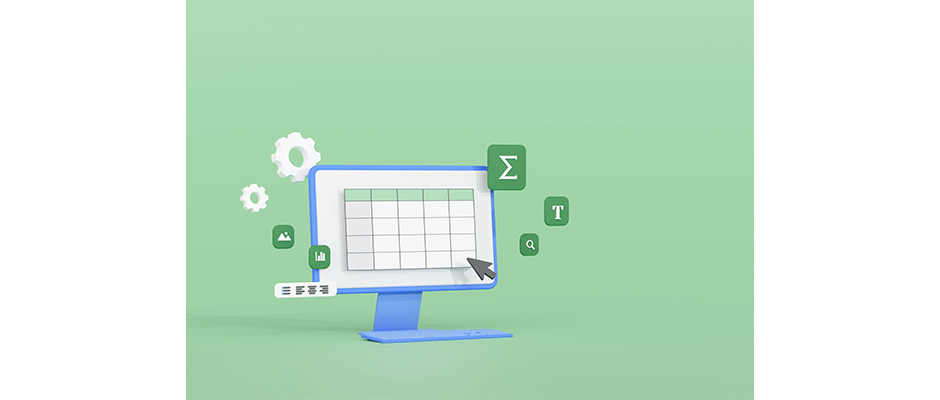業務量調査とは?3つの方法と業務改善への活用ポイントを具体例付で解説
2025.02.21
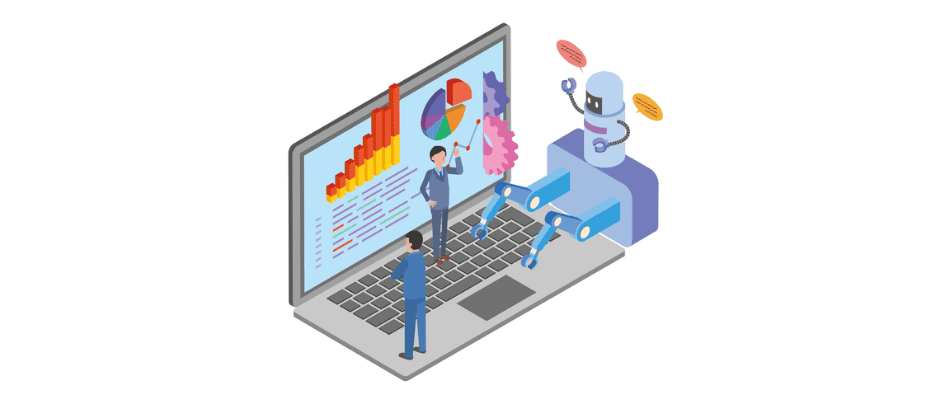
人手不足や働き方改革が声高に叫ばれている現在、多くの企業で残業削減の取り組みが進んでいます。しかしながら、「毎日残業しているのに、なかなか業務が終わらない…」「部下から人手不足の相談を受けるけれど、本当に人員を増やすべきなのか…」といった悩みを抱える企業も多いのではないでしょうか。こうした課題を解決する第一歩が「業務量調査」です。本コラムでは、業務量調査の基礎から具体的な実施方法、さらには調査結果の活用方法まで、実践的なノウハウをご紹介します。
業務量調査とは?メリットと必要とされる背景
近年、多くの企業で注目を集めている業務量調査について、その意義やメリット、実施が求められる背景までを解説します。
業務量調査とは?
業務量調査とは、組織内で行われている業務の内容や所要時間、頻度などを定量的に把握・分析する手法です。単なる業務の洗い出しではなく、「誰が」「どの業務に」「どれくらいの時間」を費やしているのかを、客観的なデータとして収集します。
例えば、営業部門では顧客との商談に加え、見積書作成、社内報告、データ入力など、様々な業務が発生します。これらの業務について、「商談準備:2時間/件」「見積書作成:30分/件」といった具合に、具体的な時間を測定していきます。また、測定データは「1日あたり」「1週間あたり」など、一定期間での集計も行うことで、より正確な業務量の把握が可能になります。
業務量調査で得られる4つのメリット
業務量調査を実施することで、組織には以下のようなメリットがもたらされます。
1.業務の可視化
部門やチーム全体の業務量を数値として正確に把握することができます。「何となく忙しい」という感覚から、「どの業務に、どれだけの時間がかかっているか」という客観的な事実が明らかになります。例えば「会議:週20時間」「データ入力:月40時間」といった具体的な数値が見えることで、優先的に改善すべき業務が明確になります。
2.属人化の特定
特定の社員に業務が集中していないか、誰しもが実施できる業務が特定の人に依存していないかなど、属人化のリスクを把握できます。例えば、「特定の担当者のみが実施可能な業務が全体の30%を占めている」といった課題が数値として見えてきます。
3.無駄な作業の発見
実際の測定により、これまで気付かなかった重複作業や非効率な作業プロセスが明らかになります。特に、複数部門での重複作業や、不必要な承認プロセスなどが具体的に把握できます。
4.残業時間の削減と人手不足の解消
効率化のポイントが明確になった結果、残業時間削減への道が開けます。さらに業務量の可視化により、適切な人員体制がわかることで、部門間での人材の再配置や採用計画の策定も可能になります。
求められる背景には深刻化する人手不足と業務過多
帝国データバンクの調査によると、2024年の人手不足倒産は342件と2年連続で過去最多を更新しました。倒産の原因は社員の退職や採用難、人件費高騰などです。人手不足を感じている企業は2024年12月時点で52.6%と半数を超えています。
このような状況下で、闇雲な採用や場当たり的な業務改善を行ったとしても根本的な解決には至りません。「どの部署で、どの程度の人手が不足しているのか」「本当に人員増強が必要なのか、それとも業務プロセスの見直しで対応可能なのか」といった判断には、客観的なデータに基づく分析と対策が不可欠であるため業務量調査の重要性が増しています。
業務量調査の3つの方法
業務量調査には主に3つの方法があります。それぞれの特徴と適切な使い分けについて解説します。
簡易測定で始める:タイムスタディ法
タイムスタディ法は、特定の期間、社員の作業を観察して時間を測定する手法です。例えば、経理部門での請求書処理業務を例に挙げると、「書類の確認:2分」「システムへの入力:3分」「承認依頼:1分」といった具合に、細かい作業単位で時間を計測します。
この手法のメリットは、正確なデータが得られることです。特に、新規プロジェクトの工数見積もりや、業務プロセスの改善検討において、信頼性の高いデータとして活用できます。一方で、測定者の人件費や、観察される社員の心理的負担といったデメリットも考慮する必要があります。また、長期的な測定には向かないため、1~2週間程度の短期間での実施がおすすめです。これは、観察者の人件費負担が大きいこと、また社員にとっても継続的な観察により通常の業務リズムを保ちにくくなるためです。
正確な把握を実現する:作業日報法
作業日報法は、社員自身が日々の業務内容と所要時間を記録していく手法です。Excel等の専用フォーマットを用意し、業務内容、開始・終了時間、成果物などを記入していきます。
この手法のメリットは、継続的なデータ収集により、業務量の推移や季節変動などの長期的な傾向を把握できることです。また、特別な機材や人員を必要としないため、全社規模での展開も容易です。一方で、記録の正確性が社員の意識に依存することや、日報作成自体が新たな業務負担となる可能性があるといったデメリットがあります。
システムを活用する自動測定法
近年注目を集めているのが、PCログ分析やRPAツールを活用した自動測定法です。この手法では、社員のPC操作ログや、利用しているアプリケーションの稼働時間などが自動的に記録されます。これにより、「営業支援システムの利用時間」「会議アプリの使用時間」「データ入力作業の所要時間」といった詳細なデータを、客観的に収集することができます。
例えばEUCツールと連携することで、詳細な業務プロセスを可視化することができます。これは、EUCツールが各社員のExcelやローコードツールなどの操作履歴を詳細に記録できるため、「どの業務にどのツールを使って、どれくらいの時間をかけているか」という具体的なデータが取得できるためです。特に日常的にPCを使用する業務が多い部署では、社員に負担をかけずに正確なデータ収集を行えるメリットがあります。
EUCに関して詳しくは「EUCとは?業務効率化を実現する仕組みと導入ステップを解説」もご覧ください。
業務量調査のプロセスと成功させるポイント
調査方法を選んだ後は、実施のための具体的な準備と運用が重要です。業務量調査を効果的に行うための実践方法と、結果の分析・活用にあたって成功のためのポイントを解説します。
業務量を正確に測定する
業務量調査の基本は、作業時間の正確な測定です。測定手法には、タイムスタディ(実測)とワークサンプリング(抜き取り)の2つがあります。例えば、経理部門での請求書処理業務では、1週間のタイムスタディにより、「入力作業:45%」「確認作業:30%」「修正対応:25%」といった詳細な時間配分が明らかになります。
この結果から、確認作業と修正対応で全体の55%を占めていることが判明し、入力時の精度向上が重要な改善ポイントであることが分かります。
測定データの収集・記録方法を統一する
データ収集時は、以下の3つの基準を統一することが重要です。
- 測定単位の統一(15分単位など)
- 業務カテゴリーの標準化
- 記録フォーマットの共通化
例えば、「資料作成」という曖昧なカテゴリーではなく、「企画書作成」「報告書作成」「プレゼン資料作成」というように具体的に分類することで、より正確な分析が可能になります。
「工数」と「頻度」でデータ分析を行う
収集したデータは、「工数」と「頻度」の2軸で分析します。特に注目すべきは以下です。
- 高工数・高頻度の定型業務
- 属人化している専門業務
- 部門間での重複業務
この分析により、例えば「週3回・各2時間かかっている在庫確認業務」といった具体的な改善ターゲットが特定でき、自動化や業務プロセスの見直しの優先順位付けを行うことができます。
属人化に関して詳しくは「属人化解消の具体的な進め方|リスク分析から効果的な対策まで」もご覧ください。
分析結果を改善につなげるためのステップ
分析結果から具体的な改善を実現するには、以下の手順を踏むことが効果的です。
1.優先順位付け
- 工数削減効果の試算:月間の削減可能時間を数値化
- 実施難易度の評価:必要な工数、スキル、コストを3段階で評価
- 投資対効果の検討:改善に必要なコストと期待される効果を比較
2.改善案の立案
- 短期的な運用改善:既存の仕組みでできる業務フローの見直し
- 中長期的なシステム化:自動化やデジタル化による効率化
- ルール・マニュアルの整備:標準化による業務品質の均一化
分析結果から具体的な改善を実現するには、まず優先順位付けを行います。各業務における工数削減効果の試算を行い、実現可能性や難易度を評価すると同時に、改善に必要な投資に対して、どの程度の効果が期待できるかを検討します。
次に、既存の業務フローの見直しによる短期的な改善や、システム化による中長期的な効率化を検討といった、具体的な改善案を立案します。立案の際は定量的な目標を設定することで、改善効果を測定しやすくなります。具体的には、「月40時間かかっているデータ入力作業の自動化」や「週5時間の会議時間の短縮」などが挙げられます。
調査結果を改善に効果的に活かすためのポイントは、現場を巻き込んだ課題の優先順位付けです。工数削減効果が高い業務から着手し、成功体験を積み重ねることで、組織全体の改善マインドを醸成できます。
業務改善を行うにあたって、詳しくは「業務改善アイデア15選!部門別の改善施策を具体的に紹介」もご覧ください。
効果を最大化するなら外部の専門家に依頼するのもオススメ
業務量調査を外部の専門家への依頼することも有効な手段です。アウトソーシングのメリットは、専門知識を持つコンサルタントが調査設計から分析、改善提案までサポートしてくれる所です。また、社内では気付きにくい課題も、客観的な視点で発見できます。さらに、社員からも「公平な第三者による調査」として理解を得やすく、より正確なデータ収集が可能になります。
特に、全社規模での大規模な調査や、複数部門にまたがる横断的な分析が必要な場合は、外部の専門家への依頼を検討する価値があります。専門家のノウハウを活用することで、調査の質が向上し、より効果的な改善につなげることができます。
◆ DBJデジタルの『業務Analyze』ならば、業務の可視化から改善施策の提案を行い、経験豊富な専門家が一気通貫でサポートいたします。
通常業務を妨げることなく、作業レベルまで踏み込んで詳細な業務把握が行うことが可能です。可視化されたデータを元に、業務プロセスの見直しやシステム改善施策の提案など、効果的な課題解決をアプローチします。詳細や興味をお持ちの方はお気軽にお問い合わせください。
業務Analyze:https://www.dbj-digital.jp/service/consulting/euc/analyze/
業務量調査は、効果的な業務改善の第一歩。正しい手法と活用で、確実な成果を
業務量調査は、「現状把握」から「具体的な改善」へとつなげる架け橋です。本コラムでご紹介した手法を活用し、自社の実態を正確に把握することで、効果的な業務改善の第一歩を踏み出すことができます。特に、人手不足が深刻化する昨今では、限られた人的リソースを最大限に活用するための基礎データとして、業務量調査の重要性が増しています。
より詳細な業務量調査の進め方や、プロフェッショナルによる支援をご検討の際は、ぜひDBJデジタルソリューションズにお問い合わせください。
 リクルート
リクルート ダウンロード
ダウンロード